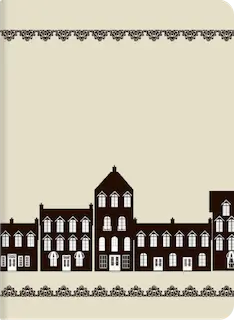_日本ではなく、イギリスとかの話しを念頭に書きます。
_バスコ・ダ・ガマの東インド洋航路の発見から、輸入する香辛料等の代わり輸出するものとして、繊維製品が持て囃され、価格が高騰しました。繊維工場は急速に増えました。人手が足りません。農家とかが急激に減ったので、労働力は、それなりにあります。男手は、鉱山とか、港湾労働とか、もっと稼げる力仕事に向かいます。消去法で、女性は繊維工業に従事する人が増えました。また、当時は農業・牧畜業では、自分の家で糸を紡ぎ、服を織るのが一般的でしたので、繊維業に従事するための基礎知識をもった女性が多かった訳です。また、当時の女性は、複数の子供を産むのが一般的なので、ある程度の年齢になると、子育てしたりしながら農業とかに従事するしかないわけです。今と違って、長時間労働な訳ですから、会社勤めしながら子育てとか出来ないですよね。そんな訳で若い女性が多い訳です。
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
詳説世界史『ヨーロッパ主権国家体制の展開』
2339
6
詳説世界史『欧米における近代社会の成長』
2271
1
【世界史】産業革命・フランス革命
443
15
【世界史】ルネサンス 一問一答
291
0