ノートテキスト
ページ1:
1章 花の作りを理解する ◎ポイント 花弁の作り 離弁花→1枚1枚花弁が離れている Date 12 合弁花→たがいに花弁がくっついてる ◎ポイントつくりの位置 中心から めしべ→おしべ 花弁がく 順番 柱頭に花粉がつくことで めしべの中心部が変化する 11 受粉 柱頭(先) めしべ 子房(ねもと) -> 中に胚珠がある おレベー やく(先の袋)→中に花粉がある ポイント 受粉後の変化 受粉前 後 胚珠 > 種子 子房 -> 果実
ページ2:
マツはどのように花が咲 マツの花のつくり ○花弁やがくはない。 ・花・雄花がある。 りん片からできている 雌花のりん片→胚珠がむき出しについている一子房がない 雄花のりん片→ 花粉のうがついている ~ 中に花粉が入ってる 花粉のう 受粉するために空気にうきやすくしている。 空気袋 -> 風媒花 虫がくる→虫媒花 。 花粉は風で運ばれ、直接胚珠につく 雌花が成長 胚珠く種子 まつかさ(2年かかる) ・裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている。 果実はできない L (例) マツ・スギ・イチョウ・ソテツなど すいをひまらしい 「スイソヒ裸子い」と覚えよう ギチョテ ウツ ツ ひま
ページ3:
被子植物・・胚珠が子房の中にある。果実ができる。 (例)アブラナ・アサガオ・サクラ・タンポポ・エンドウなど 11 花を咲かせ 種子をつくる 種子植物・花を咲かせ、種子で仲間を増やす 植物。 被子植物と裸子植物あり。 被子植物 種子植物 裸子植物
ページ4:
2章 G タンポポ 根や茎のつくりとはたらき 根のはたらき ・植物の体をしっかり支える ○水や水にとけた養分などを取り入れる スズメのカタビラ 主根・太い根 ひげ根・多数の細い根 側根…細い根 有利なこと ○主根が太いのでぬけにくい。 ○地下深くの水分を吸収している。 。 ・ひげ根がたくさんある ので、抜いても残って 子孫が残こる より多くの水分を効率よく 吸収することができる 根の先端部分抜大 小さな毛のようなもの 根毛 土の粒に密着しているため からぬけにくくなっている。 ○根の表面積が大きくなっている ため、水や水にとけた養分を吸収しやすい
ページ5:
茎のつくりと働きはどのようになってる? 茎のはたらき 道管…根から吸収した水や水にとけた養分が通る ☆植物の水の通り道 師管葉でつくられた栄養分が運ばれる管 維管束・道管と師管が集まった束 ・道管 維管束 師管 0 師管 P 維 ○ 輪のように並ぶ (ホウセンカ) A A 0 道管 散らばっている (トウモロコシ) 側外= 師管 内側=道管
ページ6:
1 植物はどのようにして栄養分をつくるのか? 光合成・植物が光を受けて、でんぷんなどの栄養分 をつくる働き。多くの植分はおもに葉 で行う 葉のつき方…上から見るとたがいに重なり合わないように ついている。 日光を多く受け、多くの栄養分をつくり出す。 2 光合成の行われる場所 ふ入りの葉を使った実験 緑色の部分 13の部分 日光が当たった アルミニウムはく ヨウ素液でむらさき色 なし 日当たる なし でんぷんあり 葉の緑色の部分 でんぷんある 変化なし あり でんぷんなし 当たらない ☆ 光合成は葉緑体で行われる 光合成が行われた 光合成が行われる場所 は日光の当たる緑色の 部分 なし
ページ7:
3章
葉のつくりと働き
葉脈…葉のすじ(維管束が技分かれしたもの)
網状脈・月の目のように広がっている葉脈
(例)ツバキなど
平行脈・平行にならんでる葉脈
(例) ムラサキツユクサなど
細胞…小さな部屋のようなもの
植物や動物の体は
細胞でできてる。
0
表側の表皮細胞がすきまなくならんでる
葉の裏側の表皮細胞のならび方は、すきまが多い
● 気孔・2つの三日月形の細胞に囲まれた小さな穴
G
葉緑体細胞の中にある緑色の粒
酸素・二酸化炭素
気孔
{
水蒸気の
この出具
○
孔辺細胞
蒸散・植物の体から気孔を通して水が水蒸気
となって出ていくこと。
○気孔の数…葉のく葉の裏 葉の裏の方が蒸散が
・気孔
ページ8:
植物の呼息と光合成 昼··· 光合成も呼息も行う 夜・・・呼吸だけ行う、光合成は× 化炭素 光合成 酸 呼吸 光合成 呼吸 二酸化炭素 酸 呼吸 酸素をとり入れ二百 炭素を出している 全体としては二酸化炭素をとり入れ、酸素を出している。 植物は昼の間、光合成と呼吸の両方 を行うが、光合成の方がさかんであ るため、全体として多くの酸素を出してい る。
ページ9:
酸化 3 化 蒸散 水蒸気 合成 気孔 吸 酸素 二酸化炭素 二酸化炭素+水 デンプン+酸素 2 B
ページ10:
4章 植物のなかま分け ○ 単子葉類 子葉が1枚 ○双子葉類子葉が2枚 9 ・さらに花弁が1つにくっついている合弁花類 ・花弁が1枚1枚離れている離弁花類 子葉の数 葉脈 茎の維管束根の形 一主根 GP 類 2 網状脈 輸のよう ・側根 子 平行脈散らばってる ひげ根 ・裸子植物 ・合弁花類 種子植物 一双子葉類 くっついてる 被子植物 千葉2枚 ・離弁花類 はなれてる 単子葉類 子葉1枚
ページ11:
株 種子をつくらない植物 胞子のう胞子がたくさん入ってる 種子をつくらない植物 シダ植物やコケ植物は胞子をつくって 仲間を増す。 シダ植物 イヌワラビ 葉の裏に胞子のうタ Whe w C ゼニゴケ 仮根 コケ植物(スギゴケもある) 胞子のう 雌株 ☆ シダ植物(例) タワラビ・ベニシダ・ゼンマイ ・生息場所…林の中の木のだけ・地面があまり 乾燥してない ・体の中に維管束があり、葉・茎・根の 区別あり。 ・仲間の増し方・・・胞子で増える。それは 主に葉の裏側の胞子のうで できる。 ☆コケ植物 (例)スギゴケ・ゼニゴケ ・生息場所…あまり日の当たらない湿った所 ・維管束ない・葉・茎・根の区別なし 水や養分を吸収 する場所 ・・・体の表面 ・根のように見えるのは仮想 体を地面に固定するため ・仲間は胞子で増える
ページ12:
植物 種子をつくらない 種子植物 被子植物 裸子植物 シダ植物 あり ・コケ植物 なし 単子葉類 ひげ根 双子葉類 主 根 胚珠むき出し 散らばってる ASK FIJAK 前のよう 網状脈 千葉 1枚 2枚 合弁花類 イ・ユリなど 離弁花類 イヌワラビ サジ・タンポポー マリ・イチョウジ アブラナ・サクラ なか
他の検索結果
おすすめノート
【1年】身のまわりの現象-光・音・力の世界-
7119
92
【中1】理科まとめ
6097
109
中1理科 【これで中1理科すべてわかる!】
1412
37
【夏まとめ】理科 中3!
1278
15
閲覧履歴
このノートに関連する質問
中学生
理科
中1の理科の植物の分類なのですが、 「ヒマワリについて、 図3の分類のどこに入るかを検討し、 その結果Fのグループに入れた。 注目した特徴は何か。」 という問題です。 理由を説明して欲しいのと、 結果的に答えが何になるのか も教えて欲しいです。
中学生
理科
解4の(1)の意味がわからないです。 答えはA→緑色 B→黄色です Bが黄色になるのは理解できますがAがなぜ青ではなく緑色になるのかがよくわかりません。 明日試験なので明日の朝までに解説お願いします🙏
中学生
理科
改めて復習してもこの問題がわからないです エ と ウ です。でもえだと、上下左右逆にならないような気がするのですけど…教えてください!
中学生
理科
果物の汁は電解質ですか?また、その理由も簡単に説明して欲しいです。お願いします🙇♀️
中学生
理科
(5)の問題の答えは葉っぱの絵からYへの矢印なのですが、葉っぱからXへの矢印ではないのですか?教えてください。お願いします。
中学生
理科
中1の火山の単元で、鉱物の種類と特徴を覚えるコツはありますか? (例:カンラン石、キ石)
中学生
理科
中1理科の問題です❕️ (3)と(5)がわかりません 🥲 教えてほしいです 🙏🏻 答えが必要であれば貼りつけるので 、 言ってほしいです
中学生
理科
中1理科です❕️ 目や耳などで受け取った刺激が脊髄を通らずに 脳に伝えられるのはなぜなのでしょうか ... ❔️ 教えてくださるとうれしいです
中学生
理科
質問です! 中1理科の問題なのですが酸素だけが入った試験管に線香を入れると一瞬で消えるのはなぜですか?? ご回答お願いします🙇♂️🙇♂️
中学生
理科
中3理科 電解質の水溶液に二種類の金属をいれ、導線で繋ぐと金属と金属の間に電圧が生じる。 なぜ、電圧が生じるのですか?よく理解できません。
News


















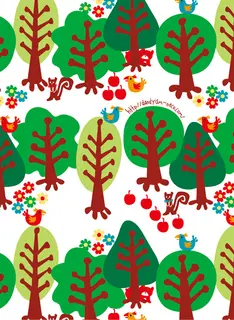









コメント
コメントはまだありません。