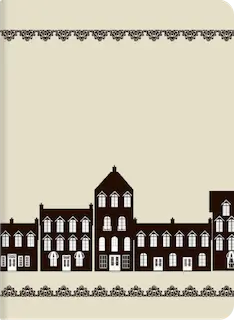Contemporary writings
高中
高一 現代の国語
「暇と退屈の論理学」という教材をやっています
「現代」や「現代社会」はどのようなものか。筆者の考えを踏まえて、説明してみる。
説明お願いします!
こくぶんこういちろう
暇と退屈の倫理学
國分功一郎
→ 関連教材
「多層性と多様性」(二
六三ページ)
国や社会が豊かになれば、そこに生きる人たちには余裕が生まれる。 その余裕には少な
くとも二つの意味がある。
一つ目はもちろん金銭的な余裕だ。人は生きていくのに必要な分を超えた量の金銭を手
に入れる。稼いだ金銭を全て生存のために使いきることはなくなるだろう。
もう一つは時間的な余裕である。社会が富んでいくと、人は生きていくための労働に全
ての時間を割く必要がなくなる。そして、何もしなくてもよい時間、すなわち暇を得る。
では、続いてこんなふうに考えてみよう。富んだ国の人たちはその余裕を何に使ってき
たのだろうか。そして何に使っているのだろうか。
「富むまでは願いつつもかなわなかった自分の好きなことをしている。」という答えが
返ってきそうである。確かにそうだ。 金銭的・時間的な余裕がない生活というのは、あら
ゆる活動が生存のために行われる、そういった生活のことだろう。生存に役立つ以外のこ
とはほとんどできない。ならば、余裕のある生活が送れるようになった人たちは、その余
裕を使って、それまでは願いつつもかなわなかった何か好きなことをしていると、そのよ
うに考えるのは当然だ。
ならば今度はこんなふうに問うてみよう。 その「好きなこと」とは何か。やりたくても
できなかったこととはいったい何だったのか。今それなりに余裕のある国・社会に生きて
いる人たちは、その余裕を使って何をしているのだろうか。
「豊かな社会」、すなわち、余裕のある社会においては、確かにその余裕は余裕を獲得し
人々の「好きなこと」のために使われている。しかし、その「好きなこと」とは、願い
つつむかなわなかったことではない。
問題はこうなる。そもそも私たちは、余裕を得たあかつきにかなえたい何かなど持って p
いたのか。
少し視野を広げてみよう。
二十世紀の資本主義の特徴の一つは、文化産業とよばれる領域の巨大化にある。 二十世
紀の資本主義は新しい経済活動の領域として文化を発見した。
5
5
かすみ
もちろん文化や芸術はそれまでも経済と切り離せないものだった。 芸術家だって霞を
*…(の)あかつきに(は)
霞を食う
127 暇と退屈の倫理学
読解編 126
る。
食って生きているわけではないのだから、貴族から依頼を受けて肖像画を描いたり、曲を
作ったりしていた。 芸術が経済から特別に独立していたということはない。
けれども二十世紀には、広く文化という領域が大衆に向かって開かれるとともに、大衆
向けの作品を操作的に作りだして大量に消費させ、利益を得るという手法が確立された。
そうした手法に基づいて利益を上げる産業を文化産業とよぶ。
「好きなこと」はもはや願いつつもかなわなかったことではない。それどころか、そん
な願いがあったかどうかも疑わしい。 願いをかなえる余裕を手にした人々が、今度は文化
産業に「好きなこと」を与えてもらっているのだから。
資本主義の全面展開によって、少なくとも先進国の人々は裕福になった。 そして暇を得
た。だが、暇を得た人々は、その暇をどう使ってよいのか分からない。何が楽しいのか分。
からない。自分の好きなことが何なのか分からない。
そこに資本主義がつけ込む。文化産業が、既成の楽しみ、産業に都合のよい楽しみを人々
に提供する。かつては労働者の労働力が搾取されていると盛んに言われた。今では、むし
労働者が搾取されている。高度情報化社会という言葉が死語となるほどに情報化が
進み、インターネットが普及した現在、この暇の搾取は資本主義を牽引する大きな力であ
けんいん
なぜ暇は搾取されるのだろうか。それは人が退屈することを嫌うからである。人は暇を
得たが、暇を何に使えばよいのか分からない。このままでは暇の中で退屈してしまう。だ
から、与えられた楽しみ、準備・用意された快楽に身を委ね、安心を得る。では、どうすれ
ばよいのだろうか。 なぜ人は暇の中で退屈してしまうのだろうか。そもそも退屈とは何か。
こうして、の中でいかに生きるべきか、退屈とどう向き合うべきかという問いが現れ
る。〈暇と退屈の倫理学〉が問いたいのはこの問いである。
〈暇と退屈の倫理学〉の試みは、決して孤独な試みではない。同じような問いを発した
思想家がかつて存在した。 時は十九世紀後半。 イギリスの社会主義者、ウィリアム・モリ
スがその人だ。
モリスが実におもしろいのは、社会主義者であるにもかかわらず、 革命志向の他の社会
主義者たちとは少し考えが違うことだ。彼らはどうやって革命を起こそうかと考えている。
いつ、どうやって、労働者たちと蜂起するか。 それで頭の中はいっぱいだ。
それに対しモリスは、もしかしたら明日革命が起こってしまうかもしれないと言う。そ
して、革命が起こってしまったらその後どうしよう、と考えているのである。
5
1ウィリアム・モリス
William Morris イギ
リスの詩人、工芸家、
社会改革家。
(一八三四一八九六]
一八七九年の講演 「民衆の芸術」で、モリスはこんなことを述べている。
129 暇と退屈の倫理学
読解編 128
革命は夜の盗人のように突然やってくる。私たちが気づかぬうちにやってくる。では、
それが実際にやってきて、更には民衆によって歓迎されたとしよう。そのときに私たちは
何をするのか。これまで人類は痛ましい労働に耐えてきた。ならばそれが変わろうとする
日々の労働以外の何に向かうのか。
そう、何に向かうのだろう。余裕を得た社会、暇を得た社会で、いったい私たちは日々 5
の労働以外のどこに向かっていくのだろう。
モリスは社会主義革命の到来後の社会について考えていた。 二十世紀末、社会主義共
産主義体制は完全に破綻したが、それはモリスの問いかけをいささかもおとしめはしない。
むしろ今こそ、この問いかけは心に響く。 「豊かな社会」を手に入れた今、私たちは日々
の労働以外の何に向かっているのか。 結局、文化産業が提供してくれた「楽しみ」に向かっ
ているだけではないのか。
モリスはこの問いにこう答えた。
革命が到来すれば、私たちは自由と暇を得る。そのときに大切なのは、その生活をどう
やって飾るかだ、と。
5
なんとすてきな答えだろう。モリスは暇を得た後、その暇な生活を飾ることについて考
えるのである。
今でも消費社会の提供するぜいたく品が生活を覆っていると考える人もいるだろう。「豊
かな社会」を生きる人間は生活を飾るぜいたく品を手に入れた、と。
2 産業革命
実はそれこそモリスが何とかしようとしていた問題であった。モリスは経済発展を続け
るイギリス社会にあって、そこに生きる人々の生活が少しも飾られていないことに強い不
満を抱いていたのである。
当時のイギリス社会では、産業革命によってもたらされた大量生産品が生活を圧倒して
いた。どこに行っても同じようなもの、同じようなガラクタ。 モリスはそうした製品が民
衆の生活を覆うことに我慢ならなかった。 講演のタイトルになっている「民衆の芸術」と
は、芸術を特権階級から解放し、民衆の生活の中にそれを組み込まねばならないという意
志を表したものだ。
つまり、モリスは消費社会が提供するようなぜいたくとは違うぜいたくについて考えて
いたのである。
モリスは実際にアーツ・アンド・クラフツ運動という活動を始める。彼はもともとデザ
イナーだった。友人たちと会社を興し、生活に根差した芸術品を提供すること、日常的に
用いる品々に芸術的な価値を担わせることを目指したのだった。人々が暇な時間の中で自
10
一二五ページ
3アーツ・アンド・クラ
フツ運動 十九世紀末
から二十世紀初めにか
けて、イギリスで起
こった美術工芸運動
いささかも・・・ない
我慢ならない
後見返し
モリスの工房
131 暇と退屈の倫理学
読解編 130
解答
尚無回答
您的問題解決了嗎?
看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉