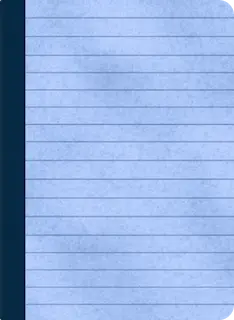Nursing
大學
看護学校の過去問なのですが答えが無く、学校も既卒のため解答の入手が出来ません。助けて下さい🥹
漢字などの調べれば分かる箇所は自分でやりますので読解系のものをお願いします🙇♀️🙇♀️
国語 (解答はすべて解答用紙に記入すること)
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校
一次の文章を読んで、後の問いに答えなさい
概念を表す抽象的な言葉を扱うことが、苦手であること。これはどの言語を用いるどの国の人にとっても、同じことかもし
れません。その上、明治維新を中心に一気に増えた近代の翻訳語が、いかにも新しい、先進的な、ありがたいものとして特別
な位置を与えられたことは、やはり日本人の言語に(1) 大きな影響を与え続けているように思います。その事情をもう少し解
きほぐしてみます。
抽象的なことばを前にすると、思考や判断の停止が起きやすい。 正しそうで権威あることばであればあるほど、その正しさ
を、自分の熟知している具体ときっちり照らし合わせることを怠るわけです。 (2) 安心し油断して、その言葉を生煮えのまま
呑み込んでしまいます。その「正しい」理論や概念を自分の具体に下ろして何事か実践しようという時がくると、 「正しさ」
こそが更なる安心や油断を生みます。 具体化が確かに意味のあるものとなっているか、という検討が甘くなる。 概念語の空転
が起きるわけです。 歯車がきちんと噛み合わないまま、 不確かな震動だけが伝わる、というような状態です。
こうしたことを避ける方法の一つとして、大村はまは(3) 「やさしいことば」を大事にさせたわけです。 抽象度の高い議論、
複雑で難解なことでも、やさしい、ちゃんと身についたことばを介在させて、なんとか理解しようとし、表現し伝え合えるよ
うに、と願ったのは、偉そうな顔をしたことばに飲み込まれないためでもあります。 偉そうな抽象語が空疎に使われている時
には、その空疎さに気づけるという力も育ちます。 これは話し言葉についても、書き言葉についても同じです。 「難しげ」な
抽象語が人の脳を空回りさせること、わかったようなわからないような、半端な状態に(a) オチイらせることを、大村は中学
生を教えながらいやというほど見続けていました。 その空転に気づかせることが、ことばの精度を上げるための第一の入り口
になっていたと思います。 「やさしいことば」で言えないことは、本当にはわかっていないことなのかもしれません。
ちなみに、私は比喩を多用していることは自覚がありますが、それも、抽象語がもたらす早すぎる納得と受容を破ろうと、
小さい爆弾を投げ込んでいるような気持ちなのです。 そして、元をたどれば、大村はま自身が比喩を巧みに用いる人でした。
使い古されて(A)並になってしまった比喩はたいして役に立ちませんが、表現力を伴った比喩は思考の空転を防いでいた
のです。
理論と実践、抽象と具体の繋ぎの不確かさは、教育現場でもしばしば見ます。国から出た (b) シシンにも、さまざまな研究
者による論文にも、「なるほど、そうだ」と思う知見が確かにあります。 しかし、それが、生きた子どもたちがずらりと居並
ぶ日々の教室で、実際に、確かに、意味のある変革を生み成果をあげることに結びついているか…..……。 そこの(c) 脆弱性はか
なり深刻だと思います。優れた理論が優れた実践と成果につながるという保証はない、ということ。 大村はまはその大いなる
弱点を現場人として痛感するからこそ、実践に徹するという姿勢を貫いたとも言えます。現実の厳しさを見切った結果でしょ
う。
逆方向((B)から(C)する場合)でも、不確かさはつきまといます。たとえば話し合うことの大切さを子どもに知
らしめたいというのは、たいへん真っ当なことです。そのために日本中の教室でなにかにつけて話し合いをさせますが、その
まとめとして「今日の話し合いはどうでしたか?」という教師の問いに、子どもはまず間違いなく「お友だちのいろいろな意
見を聞くことができて、良かったです」 というような返答をするわけです。
友だちのどの意見のどの部分を、どのように捉えた結果、「良かった」というのか、それは曖昧ですし、実はそんな実態な
どまるでないという可能性もあります。話し合えて良かった、という着地点が最初からあって、それをなぞっているだけであ
ることが多い。望ましい結論が最初から期待されていることを、子どもはかなり幼い頃から理解していて、目の前のあれこれ
の具体的なものごとを自分の目で捉え理解する際に、知ってか知らずか、(4) 大きな圧力を受けているのだと思わずにはいら
れません。期待された通りの抽象語を使って一般化するわけです。 そういう(5) 内実を伴わない発言は、言うだけ空疎さを深
めていきます。
理論と実践、抽象と具体を結ぶ線が実に不確かであること。 (D)と演繹の往還のあり方が、おぼつかないこと。これは
知を現実で生かす上で大きな弱点でしょう。 そして、その弱点の根にあるのは、言語を扱う力と態度の不十分さ、精度の低さ、
であると思われます。
大村はまの国語教室は、近代の国語教育の中でおそらく最も成果をあげた一つです。(E)、大村の仕事の成功を支えた
理論や理念は、実はそれほど驚くような特別のものではないかもしれない。誰もがわかっているような、ごく当然のこと、一
人前の言語生活者に必要な資質を丹念に育て (d) キタえていくために、(F)的とも言えるくらい当然のことを、一つひと
つ丹念に真正面から捉え、具体に移し、実行し、実現した。それをやり遂げた手際の専門性、無数の知恵と見識こそ、注目す
べきなのでしょう。 「教える」ということは、望ましいことを皆の前で述べ、「理解しなさい」 「覚えなさい」と命じ、成果
を検査し、序列をつける…そんなことではない。 望ましいその力を、必要な時に実際に使えるような形で身につけさせる、
そこまで含めて「教える」なのだ、という専門家としての覚悟がそれを支えました。
今から二三〇〇年ほども前、エジプトの王都アレクサンドリアで、幾何学の租ユークリッドがプトレマイオス1世に言った
ということば、「学問に(G)道なし」が思い起こされます。 科学技術がこれほど進歩しAIの時代が来ても、一人の人間
が言葉を身につけ、知をキタえるという挑戦に、(G)道はないのではないか。 大村はこんな言い方をしています。
「きっと、ことばの力をぐんとつけたい、急にうまくしたい、そんな方法があれば教えてもらいたいと思っているでしょう
が、なかなか、そういう急にぱっと力をつける方法はないようですね。だんだんに、そのかわり確かに、力をつけることを考
えましょう」(『大村はまやさしい国語教室』)
言語能力を育てキタえる簡単な方法はない。 たとえ権勢を誇ったエジプトの王が求めても、 また、教室に電子黒板やタブレ
ット端末が備えられても、そんな便法はない。 そう見極めた上で、 こつこつと丁寧に勉強していく。 言語に関わる神経をしっ
が、現実世界といきいきと重なることばを扱っていく。 それが、(e) 迂遠なようでいて確かな言
かり覚醒させた子どもと教
葉の教育ではないかーなんだか(H)が抜けるほど普通で当たり前ですが、 でも本当のところではないでしょうか。
(刈谷夏子『言語能力を鍛えるために』より一部改変)
傍線部(a)~(e) の漢字はその読みをひらがなで答え、 カタカナは漢字にせよ。
問一
問二空欄A・G・Hそれぞれに入る漢字一字を示せ。
問三空欄B・Cに入る適語を本文から示せ。 ただしBは2字、Cは3字の言葉である。
問四空欄に、「演繹」の対語を入れよ。
問欄に入る適語を次の中から選び記号で答えよ。
ア つまり イ そして ウ しかし
エ その上 オやはり
問六 空欄Fに入る適語を次の中から選び記号で答えよ。
ア進歩
イ退歩
ウ 革新
恒常 オ 保守
問七 傍線部(1) 「大きな影響」 とあるが、それは具体的にどんな影響か。 本文から六字で示せ。
問八傍線部(2) 「安心し油断して、その言葉を生煮えのまま呑み込んでしまいます。」とあるが、どういう意味か。この段落より
後の本文から二十字程度で書き抜き、その最初の五字で示せ。
問九傍線部 (3) 「やさしいことば」 とあるが、それに属すると考えられている表現法を本文より示せ。
問十傍線部(4) 「大きな圧力」 とあるが、それは何か。 本文より二十字程度で書き抜き、その初めの五字で示せ
~2~
問十一 傍線部(5) 「内実を伴わない発言」と反対の事柄を示している部分をこの段落以降より後の本文から、二十字程度で書き抜
き、その初めの五字で示せ
本文の内容と最も合致するものはどれか、次の中から選んで記号で答えよ。
問十二
ア歯車がきちんと噛み合わないまま、不確かな震動だけが伝わるのは、どの国の人も抽象語の扱いが苦手だからである。
イ やさしい、ちゃんと身についたことばは、複雑で難解なことばとを介在させることにより充実させることができる。
ウ 大村はまの国語教室は、ことばの精度を上げることを目標として、理論よりも実践が重んじられた教育であった。
エ 今後、教室に電子黒板やタブレット端末が導入にされ、言語に関わる神経をしっかり覚醒させていくことができる。
二 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
映画監督の黒沢清さんは高校のころ、授業が終わるや (1) いなや「映画館に逃げ込みたい」という(2) 気分で走っていったという。
そこに入ってしまえば 「映画は僕の前にボーンと出現してくれる」。自分の抱える劣等感などはもう関係なくなる。
2 映画人の思いを集め、昨秋(a) カンコウされた『そして映画館はつづく』で黒沢さんが語っている。 (3) すぐそこにある新世界、
別世界。(A) ネット経由でたくさんの作品を見られる時代でも人々は足を運ぶのだろう。
3東京や大阪で休業を(b) ヨウセイされていた映画館が今月から再開した。 舞台 (c) アイサツで吉永小百合さんが「スクリーンから
飛沫は飛びません」と語ったという。そう、スクリーンからは何も飛はず、いい映画にはこちらの(B)が飛び込んでいく。
4上映中の「ファーザー」も、知らない世界に連れて行ってくれる作品だった。(d) コンチショウの男性が主人公で、彼に見えてい
る光景がそのまま映像になっている。 娘と(e) カイゴ人の区別さえつかなくなる不安定さに落ち着かなくなる。 それでも終幕のころ
には、主人公の老いに心を寄せている。
⑤思えば映画館にしろ美術館にしろ、日常から奪われる日が来るとは想像しなかった。文化は案外もろいもので、だからだいじにし
なければと気づく。
⑤冒頭の本には映画館の副支配人の言葉もある。 コロナ禍を経て「やっぱり映画は知らない人たちと時間を(C する場所なんだ
なと思いましたね。」 (4) 言葉も交わさないのに、 一緒に見る人がいることには、ほっとする。不思議なことに。
(『天声人語』より一部改変)
問一 傍線部(a)~(e) のカタカナを漢字にせよ。
問二 空欄Aに入る適語を次より選び記号で答えなさい。
ア しかし
つまり
ウ そして
エだから
問三空欄Bに入る適語を本文より示せ。
問四空欄Cに入る適語を次より選び記号で答えなさい。
ア共感
イ共存
ウ共有
エ 共通
問五筆者の最も主張したかったことが示されている一文を抜き出し、その最初の二字で示せ。
問六
一文の中の上下が対応している (対句的な表現)一文を抜き出し、その最初の二文字で示せ。
問七傍線部(1) の 「いなや」の品詞名を次より選び、記号で答えなさい。
ア形容詞 イ形容動詞 ウ 副詞 エ感嘆詞 オ 接続詞
問八傍線部(2) 「気分」 とあるが、そうした気分になった原因を本文より示せ。
2
2
解答
尚無回答
您的問題解決了嗎?
看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉