✨ 最佳解答 ✨
主張が食い違うとは具体的にどういうことでしょうか?
この文章読ませていただいた限り,普通食い違えばすぐに勘づくと思うのですが.
ご丁寧な解説をいただきありがとうございます。
私の様な凡才で良ければお役に立たせていただきます.
まずこのペットの議題.私としてはまず出す際に定義を述べておくべきと考えます.前提が無ければ辿り着く答えが一つでも出発点が様々ということです.簡単に言えば,『東京駅に行く』という行為に対して定義を置かないと『大阪駅から東京駅まで』と考える人や『ニューヨークから東京駅まで』など無限の出発点が生まれることになります.これはサスケ様が既述していただいたことに類似するかも知れません.
私的な意見ですが,今回の食い違いを見つける人を議論を見守る議長とします.こうした時に,議長はそれぞれの主張者の感性を直ぐには理解できないです.理解できないなら,議長が幾ら主張者同士の考えの奥深くを探ったところで食い違いの原点を見出せないと思います.仮に見つけ出せたとしても,労力と見合わないと言えるでしょう.従いまして,議長の立場たる者はそれぞれの主張者へ共通の考えを持たせられるだけの会話力が必要となります.相手を知るよりも相手に理解される様に自分がなる事こそ大切だと思いますね.これは体験談であって,実際に学会に論文を投稿した時に痛切に感じた事でした.
そして最初の質問に答えるとすると,考え方の相違 (スペース) 見つけ方 で検索をかけてみると良いかもしれません.スペースを入れる事で➕の意味になります.リンクの部分をみるとよくわかりますが、仮に長々と文調の検索をかけるとヒットしませんので,細切れにされると良いと思います.あとは,図書館等で本を数冊読むと主張者のある法則性などがわかったりします.中々こちら側から相手の心理を読む事は難しいこと故ネット上では中々適切な回答が記載されていない可能性も否めません.
ありがとうございます。
相手に理解されるようになることについては、確かにその通りだと思います。言葉選び等に苦心することがあり多くの人に正確に伝わる伝え方をするのは中々難しいことですが、その大切さは日常のさまざまな場面で痛感しています。
ただ、感性を理解することの必要性については僕は懐疑的な立場です。(感性を理解する、というのは、例えばペットについて従順であることに重きを置く姿勢に共感する、という意味ですよね?)
人が人に何かを納得させようとする時、大別して感情に訴える場合と論理で訴える場合の2種類あると思うんです。前者は明らかなので後者について考えると、前提があって、更に事実による論理的な繋がりでその人の主張まで繋がっているはずです。食い違いの原点を見つけるためには、前提を知る必要こそあれど、感性を理解する必要はない気がします。
ご提示くださったようにgoogle検索をかけてみたのですが、僕の求めていた情報は見つかりませんでした。もしかしたら、リアルタイムの対人におけるその労力の見合わなさも相まって、相手と自分の前提の違いの見つけ方にフォーカスしたものは少ないのかもしれません。
1つ伺いたいのですが、「図書館等で本を数冊読むと主張者のある法則性などがわかったりします.」とはどういうことですか?














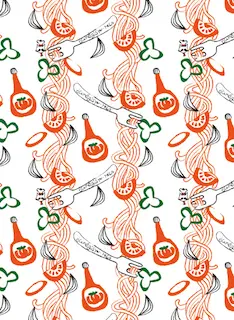
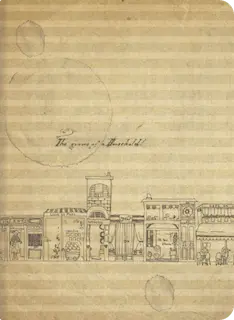


日常会話レベルでいえばそうであることが多いですし、賢い人ほどそれは無意識に行っていることが多いと思います。
例えばペットとして飼うには犬が良いか猫が良いか、という漠然としたテーマの議論では、各々が自分の基準に従って意見を言います。
A「犬が良い。飼い主に従順だからだ。」
B「いや猫が良い。静かだからだ。」
A「いや、犬は勝手にいなくなりにくいので飼いやすい」
B「猫は食費がかからないから飼いやすい」
ここで、従順であり勝手にいなくならないことが良いペットの条件であるとAは思っています。対してBは、静かで食費がかからないことが良いペットの条件だと思っています。
各々が自分にとっての真実を話しているのになぜ話が噛み合わないのか。噛み合っていないのは各々の主張より深いところ、前提となる「良いペット」の条件だったと思われます。
このように、どこでお互いが食い違っているのか、そこを明らかにする力が迅速な課題解決には大事だと思います。
この例で僕の言った「主張が食い違う」状況のイメージを掴めることを願ってますが、まだ不明な点があれば遠慮なく言ってくださると助かります。
早とちりしてBAを押してしまいましたが、このまま相談に乗ってくださると嬉しいです。