ノートテキスト
ページ1:
○トラヤヌス 帝政ローマ最盛期の五賢帝 の1人で、トラヤヌスの時代に帝政 ローマの領土は最大に。 〇パウロ 初め、パリサイ派に属したキリスト 教徒を迫害したが、イエスの刑死後 ②心し、キリスト教をローマ帝国 各地に布教した。 ○イタリア半島に侵入した西ゴート ローマを破壊し、その後 イベリア半島に侵入して 西ゴート王国を建国した。 〇ノルマンディー公ウィリアムは、 1066年にイングランドを征服し、 ウィリアム1世としてノルマン朝を 開いた。 ○コンスタンティヌス 迫害を受けていたキリスト教を 313年にミラノで公認することで、 ローマ帝国の統一をはかり、330年に 首都をローマからコンスタンティノープル に移した。 ○オットー1世は2度イ を行い、教会を助けたので、 962年に皇帝となり戴冠された。 これに成立した国を神聖 ローマ帝国と称するようになった。 ○ローマ教会とコンスタンティノープル 教会は、726年にビザンツ皇帝 が聖像禁止令を出したことを 最初の契機として対立し、1054年 に互いに破門しあった。 800年:教皇レオ3世がカール大帝に ローマ皇帝の帝冠を与える 862年:リューリクがノヴゴロド国を建国 962年:オットー1世が神聖ローマ帝国 皇帝となる。 1038年=トゥグリル=ベクがセルジューク 朝を開く
ページ2:
古代ローマ ・都市国家ローマでは、エトルリア人の王が追放され、 前6c末には貴族共和制が樹立された。やがて、 政治的発言を強めた平民は、貴族と激しく争うよう になり、最終的に前287年のホルテンミウス法の制定 により、貴族と平民は 平民会の議決は元老院の 法的に平等になった。承認なしに法律になる 前272年にギリシア人の植民市タレントウムを陥落させ イタリア半島を統一したローマは、その後ポエニ戦争に ポリビオス『歴史』 分割統治 勝利しまた東地中海諸国も征服して地中海の支配 を確立した。しかし、長年の従軍と属州からの安価な 騎士が台頭 穀物の流入によって中小農民は没落し、一方で有力者は ラティフンディアによって豊かになるという社会矛盾が深まった。 奴隷使用の大農場経営
ページ3:
前27年に帝政を開始したローマは、マルクス=アウレリウス= アントニヌスまでの間、安定と繁栄を続『自省録』 けたが、3cには軍人皇帝時代となり、北からはゲルマン人 東からはササン朝などが侵入するetc「3世紀の危機」を迎えた。 コンスタンティヌスは、325年ニケーアで最初の公会議を召集 そこにおいて三位一体説をとるアナタシウス派が正統とみな され、アリウス派は異端とされ、ゲルマン人の間に伝達された。 4c後半には背教者” キリスト教は父なる神につくられたもので 神と同質ではないとして人間性を強調 ユリアヌスが異教 復興を企てるという動きがあったが、キリスト教徒の勢いを 止めることはできなかった。
ページ4:
・神聖ローマ帝国 ハインリヒ4世(ザリエル朝) →カノッサの屈辱 (1077) ・フリードリヒ1世(シュタウフェン朝) →第3回十字軍参加 ・大空位時代(1256~73) →無皇帝状態。ルドルフ1世即位で終結 ・カール4世(ルクセンブルグ朝) →金印勅書 ・ハプスブルク家帝位世襲化(1438~1806) ウマル 初めはメッカで預言者ムハンマドを 迫害。 後にムスリムとなり、第2代に カリフとなった。 ©Disney アーウィ301928 RLANDO, FL. 了総督に就任して支配地を 660年、イェルサレムでカリフ 手を宣言。実子を期かつに指名し 世襲化の道を開いた。 フリー カリフに就任したが対抗勢力との 抗争に終始。ハワーリジュ派に暗殺 された後、彼の支持者はシーア派と 称されるように。 ウスマーン クライシュ族のウマイヤ家出身で、 長老会議の互選により第3代 カリフに就任。
ページ5:
イタリア半島に進入した西ゴート人 はローマを破撃し、その後 イベリア半島に侵入して西ゴート 王国を建国した。 ノルマンディー公ウィリアムは、 1066年にイングランドを征服し、 ウィリアム1世としてノルマン朝を 開いた。 中世ヨーロッパ sweet ローマ教会とコンスタンティノープル 教会は726年にビザンツ皇帝が 聖像禁止令を出したことを最初の 契機として対立、1054年に互い に破門しあった オットー1世は2度イア遠征を行い. 教会を助けたので、962年に皇帝として 戴冠された。 この冠に成立した国を 神聖ローマ帝国と称するようになった。
ページ6:
コ エジプト 969.イスマーイール派の首長が新しい王朝を造り、第4代のカリフ のムイッズはフスタートの北郊に新都カーヒラを建設 1260 マムルークから身をおこしたバイバルスはスルタンに即位し、ヒジャーズや ヌビアに遠征するとともに、バリードとよばれる駅逓網を整備 1538 グジャラート王国の救援要請を受けたスレイマン=パシャは、 インド洋遠征を行い、その帰途、イエメンの要衝である ザビードを征服した。 1770~71. エジプトの自立化を進めようとしたアリー=ベイは、メッカの 保護権に干渉し、さらに宗主国の混乱に乗じてミリアを 攻略しようとした ルネサンス ボッカチオ デカメロン ・リアリズム スダンテ ・神曲 ・トスカナ語 エラスムス 愚神礼賛 ・教会の腐敗風刺 マキャヴェリ 君主論 ・イタリア統一
ページ7:
4c後半、アジア系のフン人が東方から侵入し、黒海北岸にいた ゲルマン人の一派である東ゴート人を征服し、さらに西ゴート人に せまるというできごとが起こった。 そこで西ゴート人は南下をはじめ、376年にはウツをわたって ローマ帝国内に移住した。 これをきっかけにして、他のゲルマン人の移動をはじめた。 北ガリアにはフランク人が移動してフランク王国を建て、 アングロサクソン人はブリテン島にわたり七王国を建てた。 この間帝政ローマは東西2つに分裂し、西ローマ帝国はこの 民族大移動の混乱の中で、476年にゲルマン人の傭兵隊長 オドアクルに滅ぼされた。 セルバンテス ・ドンキホーテ スペイン レオナルドダヴィンチ ・最後の晩餐 万能の天才 トマスモア ・ユートピア ・理想社会
ページ8:
sweet 宗教改革!!!! S ドイツでマルチン=ルターが宗教改革をおこしたのは1517年である。 次いでフランス生まれのカルヴァンが聖書研究に影響を受け、 弾圧を避けるためにスイスに亡命し、改革運動を行った。 カルヴァンは予定説で各人の救済は神により定められていると主張し、 禁欲的態度で職業労働に励むことを奨励したので、新興市民 階級の間に営利活動の精神的支柱として広まった。 この信徒はフランスではユグノー・ネーデルランドではゴイセン イングランドではピューリタンとよばれた。 これらに対して旧教徒側も改革を始めた。 ・この運動を対抗宗教改革という。 スペイン出身のイグチティウス=ヨロラが中心となりスペインの植民植 事業と並行して海外伝道を進めた。 ・1549年に日本に来航したザビエル、中国で布教活動をしつつ、 坤輿万国全図』を作ったマテオニリッチなどが有名。
ページ9:
イギリスの議会政治 議会主義に基づく民主政治が他の国に先駆けて発達した イギリスであるが、それは13c初めにジョン王の王権濫用を防止 するためにマグナカルタを制定したことに始まる。 これはイギリス王室の根本的な在り方田国もまた法に従う」ということも 示唆したものであった。 その後17cに入り2つの革命が起こり、議会政治が確立した。 ステュアート朝のチャールズ1世が国教に従わない新教徒を圧迫し、 議会を無視したことで内乱が発生し、クロムウェルを指導者とする 議会派が勝利をおさめ、共和政が一時実現した。 この革命をピューリタン革命という。 1660年、王政復古となって、チャールズ2世が即位すると、王の カトリック復活を恐れた議会は審査法人身保護法を制定した。 次いで即位したジェームズ2世も専制の強化を図ったので、議会 はオランダから新しい国王ウィリアム3世、メアリ2世を迎え、 権利章典を発布させた。 これを名誉華名という。 こうして、イギリスは2つの革命を通じて議会政治を確立した。
ページ10:
ルネサンス ルネサンスは14cにイタリアの都市フィレンツェで始まり、 15~16cにヨーロッパ各地に広がっていった。 その根本精神は人文主義であり、人間のありのままを 肯定する考え方が浸透した。 16cになると、万能の天才とよばれたレオナルドダヴィンチ、 彫刻・絵画・建築などに優れた業績を残したミケランジェロ、 肖像画や聖母子画に優れた作品を残したラファエロの距巨匠 が活躍した。 また、この時代の文化運動は、技術や科学の分野でも大きな 発展を遂げた。 特に、火薬、羅針盤、活版印刷はルネサンスの時代に改良され その後の世界の進展に多大な影響を及ぼしている。 絶対王政 ・オランダでは、オラニエ公ウィレムを指導者として、スペイン ●からの独立が達成された。 ・独立後は、アムステルダムを中心に急速な経済発展をとげ、 1602年には東インド会社を設立し、香料の産地である 東南アジアに進出した。
ページ11:
1830_ 七月革命 1815. 安全会議、終わる)この頃ギリシャ独立 1848. 二月輪が終わる 1853. クリミア戦争 1857. シパーヒーの友 → ムガル帝国滅亡 1861. アメリカ南北戦争 1871. ドイツ帝国成立 カンザス・ネブラスカ法(いちり) カンザス州・ネブラスカ州が連邦にな 盟するとき、住民投票で奴隷州か 自由・かを決定することを定めたもので、大泉町文 奴隷制体制派と反対派の対立が 激化した。 ホームステッド法(1862) リンカン大統領の政策であり、西部の 貧しい開拓農民に、手数料程度で 開ぐり鮮 公有地で分けたもの。これによって、西部 での自作農創設と、西部農民の北部への 支持を取り付けようとした。 ミズーリ協定(1820) 北緯36度30分以北の新しい 州は奴隷制を認めないと したもの。
ページ12:
第一次世界大戦 の 第一次世界大戦は国同士の対立に加えて、それとつながった 民族相克の問題などを原因とし、中小国や植民地をも 巻き込み世界的規模のものとなった。 この大戦はロシア・オーストリア=ハンガリー帝国・ドイツ帝国の三帝国の 崩壊によって終結し、このときロシアからはフィンランド・エストニア ラトヴィア・リトアニアが、オーストリア=ハンガリー帝国からはチェコスロバキア、 ユーゴスラヴィアが独立した。 この戦争はアメリカや日本の台頭、ソ連の出現などヨーロッパの 世界政治に占める比重を低下させたこととなった。自 また、この社会不安の中から実存哲学という哲学が生まれた。 人類史上類をみない惨禍をもたらした大戦を体験した人には 恒久平和を願望するようになり、アメリカ大統領ウィルソンが 提唱した十四条に基づき、国際連盟が設立された。 実存主義哲学者 著作 人名 特徴 ヤスパース(独) 中学』 ユダヤ系で反ナチス ハイデッガー(独) 『存在と時間』 一時ナチスに協力 サルトル(f) 「存在と無』 五月危機に同調 嘔吐』
ページ13:
19c末から20c初頭にかけて、イギリスはアフリカ縦断政策をとり、 ケープタウンからカイロを経て、インドのカルカッタに至るという 3C政策を実現しようとした。 その頃フランスは、サハラ砂漠からインド洋に至るアフリカ横断政策を とったので、この両国はスーダンの一角で衝突して、1898年にいわゆる ファショダ事件が起こった。 しかしこの両国はその直後から新興のドイツに対抗して協力するよう になり、第一次世界大戦では連合してドイツと戦った。 19c末から20c初頭のドイツは、アフリカに進出して1905年と1911年 フランスとの間に第一次、第二次モロッコ事件をおこし、また中近東に 進出しようとしてベルリン、ビザンティウム、バグダードを結ぶ3B政策 をとってイギリスと対立した。 他方ロシアは、日露戦争の敗北以降、バルカン半島での南下政策を 推進してドイツ、オーストリアと対立した。 他方ロシアは、日露戦争の敗北以降・バルカン半島での南下政策 を推進してドイツ、オーストリアと対立した。 第一次世界大戦の直接の原因は、皇太子夫妻の暗殺に反発した オーストリアと、ロシアに後押しされた南スラヴ人の国セルビアとの 開戦であった。 大戦による打撃はロシアとドイツ及びオーストリアにおいて深刻であった。
ページ14:
ロシアでは1917年に革命がおこってロマノフ朝が倒れ、やがて ルーニンを首班とするソヴィエト政権が成立した。 文学革命 1917年に白話運動を中心に展開した 文学・思想革命で、儒学思想を批判し、 家族制度に基づく古い価値体系を 動揺させた。 日露戦争で日本がロシアに勝ったと考えた アジア諸民族の中には、日本の近代化を モデルに立憲革命を目指す動きが高まった ところもあった。 こうした中で、インドは国民議会が4大綱領 を決議するなど宗主国への対決姿勢を 強めた。 中国同盟会 義和団事件 1905年に孫文が日本の東京で これがきっかけで日露戦争の背景 組織した革命組織 となったロシアの中国出兵と駐留 を招いた
ページ15:
中国古代 ☆武帝は西域経営を積極的に進め、大月氏に張騫を 派遣したのを手始めとし、大遠征を行った。 この他武帝は郷里選による官吏任用を行い、中央集権化を 進めて皇帝の権力を強化した。前美 前時代末期より使用され始めた鉄製農具は、中耕の発明 と相まってこの時代には農業生産力を著しく増大させ、また、鉄製 農具の普及に戦闘法にも変化をもたらした。戦国時代、 ☆後漢書によれば、大秦王安敦の使者が海路日南郡を訪れた。 大秦王安敦とは、マルクス=アウレリウス=アントニヌスを指していると 考えられており、この大秦という国は、西域都護班超が部下の 甘吏を西方に派遣したことより知られるようになった。後漢 ☆王の政は中国統一をなし、この権威を示すものとして王という 称号をやめ、皇帝と称した。
ページ16:
社会契約説 ホッブズ リヴァイアサン』 「万人の万人に対する闘争」 絶対王政を擁護 ロック 市民政府二論』 ・抵抗権 ・革命権 アメリカ独立宣言 ルソー 『社会契約論』 「自然に帰れ」 一般意思 ・直接民主主義 自然法 あらゆる時代や社会を通じて 拘束力をもつと考える法 福祉国家の実現 国の自由放任策が富の偏在を招き、 社会的・経済的弱者の救済や最低 限度の生活の保障が必要となったため、 福祉国家の実現が求められている。
其他搜尋結果
瀏覽紀錄
與本筆記相關的問題
News
























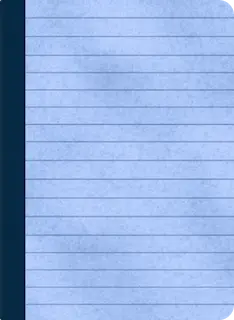
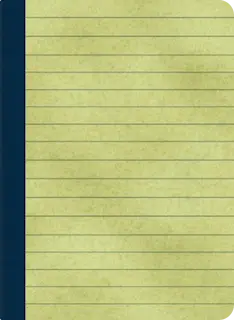





留言
尚未有留言