✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
なぜこの名前になったかというと、「その年に起こったから」です。
壬申の乱は、「壬申の年」に。
戊辰戦争は、「戊辰の年」に。
甲子園は、「甲子の年」に出来たからです。(十干と十二支の、それぞれ最初の「甲」と「子」が出会う年だったからです。60年に一度のことです)
これがどの年か?というのは、ちゃんと計算方法があるんですね、
「壬申の乱」を例に説明します。
まず、(西暦+7)÷10の、余りを出します。
壬申の乱は672年ですから、
(672+7)÷10=67...9ですね。
余りは9です。
十干で9にあたるのは、「壬」です。
次に、(西暦+9)÷12の、余りを出します。
(672+9)÷12=56...9です。
余りは9です。
十二支で9にあたるのは、「申」です。
これを合わせて、「壬申」の年です。
戊辰戦争や甲子園も、この計算方法で出された干支によって名付けられています。
一度、計算してみてください。
十干
甲:1
乙:2
丙:3
丁:4
戊:5
己:6
庚:7
辛:8
壬:9
癸:0
干支
子:1
丑:2
寅:3
卯:4
辰:5
巳:6
午:7
未:8
申:9
酉:10
戌:11
亥:0
回答本当にありがとうございます。一つ質問なのですが、なぜ十干を選ぶときは西暦+7÷10で十二支は西暦+9÷12なのでしょうか。おしえていただけると助かります。
ウロ覚えなので、正確ではないかも知れませんが、
西暦と干支のずれを直すためと聞いた気がします。
干支は中国が起源。
西暦はヨーロッパが起源。
西暦元年=甲子、ではないんですね。
そのズレを直すために、7または9を足すのだと思います。
10で割るのは十干だから、12で割るのは十二支だからですね。
理解できました。すごく助かりました🙇♀️ありがとうございます。
















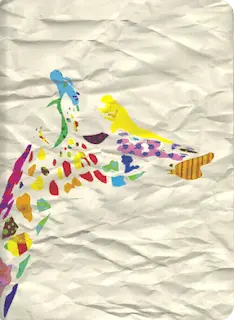
最後の数字のところ、「干支」になってますね💦
正しくは、「十二支」です。