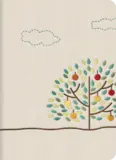✨ ベストアンサー ✨
どんな科目であっても、その勉強法が基本になると思います。
強いて言うなら、教科書で勉強する時から、ちゃんと図を見ておくことが大事だと思います。本屋に行けば一問一答を謳った問題集もありますが、そういう文字だけ見て単語だけ覚えるような勉強ではなくて、普段から資料集に載っている図を自分で解釈して説明できるようにするべきです。また、この問題を見てもわかるように、地名ではなく必ず地図で出題されるので、普段から地図帳で場所を確認しながら勉強するべきです。
昔と比べて、必要な知識が増えたわけではないので特殊な勉強は必要ありません。ただ、図から得られる情報の中から、特徴的な部分を見つける力が問われるようになったというだけです。その練習は過去問を解く中でできますが、いくら図から特徴を読み取れたとしてもその特徴が現れる理由が分からなければ結局問題は解けないので、今は必要な知識を頭に入れることを優先すべきです。