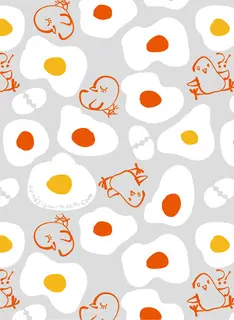地図の中の数字は標高を示しているので、数字に印をつけます。
そして、等高線の数を数えて、主曲線の間隔がどれだけかを考えます。
地図の下の方に、「46.6」「74」という数字があります。
等高線をなぞってみて、この数字をヒントにして等高線が何m間隔かを考えて、10m間隔だとするとうまくいきます。
地理
高校生
これがなぜ10メートル間隔で引かれた主曲線なのかが分からないので教えてください!
地理B
問6 国土地理院は、ウェブ上で地理院地図のほか,さまざまな自然災害に対応した
✓「重ねるハザードマップ」を公開している。 次の図7は、大雨による水害を繰り返し
てきたある河川の中流域を示したものであり、後の文タ~ツは,図7中のS~Uの
いずれかの地点で「重ねるハザードマップ」により想定される水害の内容を示した
ものである。S〜Uとタ~ツとの正しい組合せを,後の①~⑥のうちから一つ選べ。
7
地理院地図により作成。
S
T
U
【S~Uのいずれかの地点で想定される水害の内容】
スタ洪水によって想定される浸水深:0.5 m 未満
チ洪水によって想定される浸水深:5.0 ~ 10.0m
ツ ため池決壊による危険性: 区域内
① ②
タ
チ
ツ
タ
ツ
図 7
チ
チ
タ
ツ
チ
ツ
タ
11"
ツ
タ
チ
11
ile
⑥ ツ
チ
タ
問6 07 正解 ②
地点Sは, 河川に近接するものの, 河岸との間に
2本の等高線 (10m間隔に引かれた主曲線) が見
えることから、洪水時でも浸水しにくい高台に位置
していることがわかる (タ)。 河川の南岸には台地
が広く分布するが,地点Tは、その西向きの谷に位
置している。 河川と距離が離れており, 等高線2本
分の標高差も確認できるので洪水の被害は及びにく
いが、谷の上流側(南東方向)にため池が見えるこ
とから,大雨によるため池決壊には警戒が必要であ
る(ツ)。 地点Uは,河岸との間に畑が営まれてい
る微高地が分布するものの, 河川との標高差がほと
んどない。そのため, 洪水発生時には水が流れ込み,
浸水深も大きくなると考えられる (チ)。 なお、地
点Uの方がため池に近いが,間に尾根筋があること
から、ため池決壊による浸水は想定されない。
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉