他の検索結果
おすすめノート
西洋史概説 1
42
0
このノートに関連する質問
大学生・専門学校生・社会人
歴史
リンディスファーンの福音書について解説して頂きたいです。どういった内容なのか、何を伝えたいのか、どのような時代背景の元書かれたものなのか。また、英語の歴史においてどのような影響を与えたのか。についてお願いします。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
どのように回答していけば良いか分かりません。 教えていただけると嬉しいです。 下線部の内容は気にしなくて大丈夫です。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
中世の武家社会に関する記述として最も妥当なのはどれか。 1 12世紀には,源頼朝が鎌倉を根拠地と定め,東国の支配を進めた。頼朝は鎌倉に侍所,公文所(政所),問注所などを設置し,さらには朝廷から地方に守護と地頭を置く権限も認められ,武家政権としての鎌倉幕府を確立させたが,その当時,依然として京都には公家政権が存在し,律令体制による伝統的な行政権を保持していた。 2 源頼朝の死後,征夷大将軍に任命された北条時政が鎌倉幕府の実権を握り,新たに京都に西面の武士を置いて朝廷の監視を強化したことから,幕府と朝廷との対立が深まり,承久の乱が起こった。その結果,幕府側が圧倒的な勝利をおさめ,それまで幕府の力が弱かった畿内や西国にもその支配権が浸透することになった。 3 承久の乱後,急増した荘園領主と地頭との紛争などを公平に裁判するため,武家法として最初の体系的法典である武家諸法度が制定された。これは,武家社会の道理・習慣や源頼朝以来の幕府の先例を基準として,御家人の権利・義務や裁判の原則を定めたものであり,朝廷や荘園領主の裁判をも規制するものであった。 4 鎌倉幕府の滅亡後,後醍醐天皇は京都で公武を統一して新しい政治を始めた。天皇は足利高氏(尊氏)を征夷大将軍に任命して室町幕府を開かせたが,北条早雲が反旗をひるがえして京都に光明天皇を立てたことから,南北朝の動乱が始まった。この動乱の中で将軍権力は急激に弱体化し,幕府の実権は有力な守護大名へと移っていった。 5 16世紀には,戦国の争乱の中で守護大名が没落し,新たに新田義貞や楠木正成などの戦国大名が台頭してきた。戦国大名は一族や国人・地侍に知行地を与えて家臣とし,大名と家臣とは土地の給与を通じて御恩と奉公の関係によって結ばれるようになった。こうして,それまで武士の間で私的に結ばれてきた主従関係が,公的な関係へと変わっていった。 正解と間違っているものはなぜ間違っているのか教えていただきたいです。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
大学の課題でわからなくて困っているので助けて欲しいです! 中世盛期の西欧都市において、同業組合が形成されることになった経緯を、教えてください。できれば、キリスト教との関係も教えてください。 600字〜1200字でまとめていただけるとありがたいです。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
3.社会主義者は、「個人主義」的な自由主義に懐疑的で、生産手段の公有化など、「社会化」の重要性を主張した。 ○×でお願いします。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
1.18世紀後半から19世紀にかけて政治参加を求める運動は議会改革の要求として発展して、定数是非や選挙資格の見直しを求める運動が盛んになった。 2.1832年の議会改革は、自由主義的な展望に従って、国家の将来像を見据えた人々によって実現したと考えられている。 それぞれ○×でお願い致します。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
イギリスにおいて、フランスのような大規模な政治的な革命が 18世紀末から19世紀にかけて、発生しなかった理由を、 政治的な仕組みと経済、社会的な観点を踏まえて、論じてください。 お願い致します。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
○×でお願い致します。 1.産業革命は、世界に先駆けてイギリスで発生した。 2.イギリスでは、労働者の賃金が周辺諸国より安かったので、工場で労働者を大量の雇用することが容易であった。 3.イギリスが三角貿易で蓄えた富は、産業革命の原初的蓄積として、産業革命の最初期に工業を主導した鉄鋼業を開始する重要な資本となった。 4.当初発明された機械の中には、ジョン・ケイによる飛び杼があった。この機械により、綿織物の大量生産が可能となり、綿糸の需要が大幅に増加した。 5.機械の発明を受けて、それらを動かす動力の開発が進んだ。上記期間の発明は、当初、紡績機に利用されたが、後に、他の分野にも応用が進んだ。 6.イギリスでは、議会の課税承認権が確立していたことが、かえって、国王にとって、効果的な徴税を可能にした側面が指摘されている。 7.18世紀後半から19世紀にかけて、政治参加を求める運動は議会改革の要求として発展して、定数是正や選挙資格の見直しを求める運動が盛んになった。 8.1832年の改革で、納税資格が明確となり、有権者は増加した。また、腐敗選挙区などが廃止されたこともあって、定数の再配分が実現した。 9.議会改革により新たに選挙権を得たブルジョワジー層の影響力が政治おいて高まったと考えられる。その象徴的な事例として、1846年に、穀物法が改正が挙げられる。 10.1832年の議会改革は、自由主義的な展望に従って、国家の将来像を見据えた人々によって実現したと考えられている。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
フランスにおける絶対王政とは、その名の通り国王が国王が絶対的な権力を有し、全ての政策において自ら独断的に決定を行う体制であった。 この場合は○×どちらでしょうか。 全ての政策においてなのかが分かりません。 全てなのか、全てではないのか。 回答よろしくお願い致します。
大学生・専門学校生・社会人
歴史
○×でお願いします。 Q1,フランスにおける絶対王政とは、その名の通り国王が国王が絶対的な権力を有し、全ての政策において自ら独断的に決定を行う体制であった。 Q2,1789年とは全国名士会が招集された年であるとともにパリの民衆がバスティーユ監獄を襲撃した年である。 Q3,1789年に出された「人権宣言」はフランス革命の目標を示す文書として評価され、後に1791年に制定された憲法ではその全文として位置づけられた。 Q4,周辺諸国の干渉や国王の逃亡事件により急進派の影響力が強まり、民衆層の助力も得て権力を握った強硬派は、1793年に新たな憲法を制定して、社会権や男性普通選挙など、当時としては急進的な内容を盛り込んだ。 Q5,ナポレオンの統治下で、全国の自治体は県知事が派遣され、中央主権的な国家が形成された。 Q6,ナポレオンの海外遠征により、イタリアやイギリスはフランスの統治下におかれ、フランスと類似の制度が導入されることとなった。
News

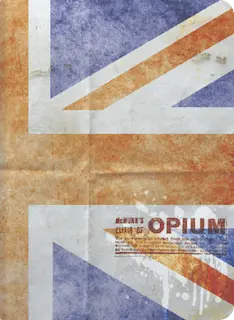





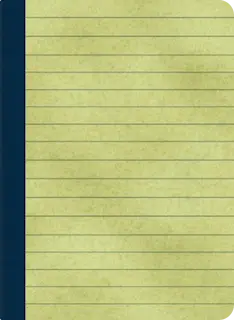
コメント
コメントはまだありません。