✨ 最佳解答 ✨
まず図のように補助線を引いて、緑、橙、青で囲った三角形を考えます。これらの内角の和は540°です。(この手順を①とします)
次にこれらの三角形の内角となっている角と、もともと問題で指定されていた角を比較します。そうすると、図のA、Bの角はもともと問題にあったのに①では含まれておらず、また角E、Fはもともと問題になかったのに、①で含めてしまった角です。
なので、次に角A、Bと角E、Fの関係を考えます。そのために図のように角C、Dを考えると、ABCDを頂点とする四角形で考えればその内角の和は360°だから、∠A+∠B+∠C+∠D=360°となります。
また図より、∠C=180°-∠E、∠D=180°-∠Fなので、上の式より、
∠A+∠B+(180°-∠E)+(180°-∠F)=360°
整理すれば、
∠A+∠B= ∠E+∠F
となって、①で内角の和を求めるときに余計に含めてしまった ∠E、∠F と、含めなければならなかったのに含めなかった ∠A、∠B の角の大きさは等しいことがわかったので、
結局①で求めた内角の和が、求める角の和となり、答えは540°となる。
これでいいかな?
けっこう疲れました。
あっ、でも何となく理解出来ましたー!
ありがとうございます!
小学生だと∠をまだ習ってないのですね!
すみません。
でも理解していただけたなら嬉しいです!
小学生の算数(中学受験の問題?)ってこんな難しい問題があるんですね、知りませんでした。
中学受験頑張ってください!
















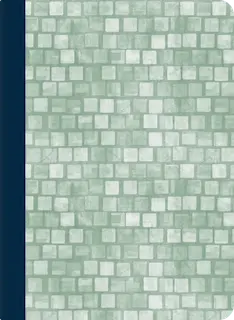
∠ってどう使うんですか?小学生なのでまだ分からずに……😭