ノートテキスト
ページ1:
第1章 生物と光 P14~ A植物の生育と光 P14~ ①食物のもとをつくる葉緑体 P14 「ヒト→動物の仲間である。自分で水や二酸化炭素の無機物から デンプンなどの有機物をつくることはできない。 植物 光合成によってつくった有機物や、それをもとにして他の生物がつくった有機物 水・塩類などの無機物を食物としてとり入れる。 ↓ 光合成を行っているのは・・・ 光合成を行っているのは、葉緑体という小さな粒が見られる。 ヒトを含む動物の細胞は葉緑体がない。 P14 図1. 植物細胞 動物細胞 0 核 細胞膜 葉緑体 液胞 細胞壁 ②光合成と光合成産物 P16 大気中→0.04%の二酸化炭素が含まれる。植物は二酸化炭素と根から吸い上げた水を 原料とし、太陽の光エネルギーを吸収してデンプンなどの有機物をつくる。 その際酸素が発生する。⇒光エネルギーを利用するので光合成とよばれる。具合 光合成の表し方 CO2 + H2O +光エネルギー→有機物+02 (二酸化炭素)+水 (酸素) 光合成でつくられた有機物は、水に溶けやすい物質に変換されて 植物体の各所に運ばれ、セルロースやデンプンなど様々な物質に変換され、 植物の成長や繁殖に使われる セルロース 細胞壁の主要な構成部分で、植物繊維を形成として 植物体を支える。⇒人間生活になくてはならない デンプン→種子や茎・根などに蓄えられ、植物のエネルギー源になる。 人間⇒米や麦、いもなどを食べることで、多量に含まれるデンプンを エネルギー源などにしている。
ページ2:
Cate ノート続き② ③光合成色素 P17 光合成が行われる際に、光エネルギーをとらえるのが光合成色素である。 主な役割 クロロフィルという緑色の色素で、赤と青の光を強く吸収する。 緑色の光→ほとんど吸収されないので光が透過したり反射したりする結果 クロロフィルを含まれる葉は緑色に見える。 緑色の葉→光合成色素として赤黄色のカロテンや黄色のキサントフィルと よばれる色素も含まれる⇒様々な色の光が吸収。 いろいろ色の光がどれだけ光合成が行われているかを調べると、 光合成色素が吸収する光の波長とほぼ一致。 ④光の強さと光合成P17 光合成速度は光の強さの影響を受ける 植物を呼吸によって二酸化炭素を出しているので、暗黒では、光合成による 二酸化炭素の呼吸は見らない。呼吸による放出は見られる 光を強めると、光合成による二酸化炭素の呼吸は増えていく。 ある一定の強さで二酸化炭素の呼吸と放出の量は等しい ⇒二酸化炭素の出入りはなくなる このときの光の強さを光補償点という。 光補償点より強い光がない植物は成長しない 光が強いと光合成はさらに増加していく、やがて一定になる。 このときの光の強さを光飽和点という。 光合成速度は計測された二酸化炭素の呼吸速度(見かけの光合成速度)に 呼吸による二酸化炭素の放出速度(呼吸速度)を加えたもの P17 図5 CO2 吸収 速度 光飽和点 光合成速度 見かけ 光合成速度 CO2 光補償点 呼吸速度 放出速度
ページ3:
ノート続き ③光大気 P/6 図2 P17. 酸素 「光合成有機物」 二酸化炭素 水 葉緑体 ・デンプン 七セルロース、デンプンなど ↓ 成長・繁殖 ①繊維(ワタ)②穀類(イ)③材木(スギリ →衣類、食料、住居に利用、 図4 1100 ・光の波長と 光合成速度 80 の ・関係を示す. 60 40 光合成速度 光の吸収玄 100 & 60 60 ti 40 200 0 400 2 クロロフィルb. 緑 カテン 赤黄 20 クロロフィルム 青緑 紫青緑黄橙赤 500 600 700
ページ4:
Doto ノート続き、 ④光の強さと光合成-2 P20 光補償点や光飽和点は植物の種類で異なる。 ヒマワリやタンポポのように日なたを好んで生育する植物は陽生植物とよばれ、 光補償点が高く、光飽和点も高い。 アオキやイヌシダのように日陰でも生育できる植物は陰性植物とよばれ 光補償点も光飽和点も低い 1本の木でも、日なたにある葉は分厚く、日陰にある葉はうすい これらを陽葉、陰葉という。 P20 図6 光飽和点 CO2の 吸収 速度 光補償点 光の強さ 図7 陽葉 日当たりのよいところに、 陽菜ができ、葉が分厚い ・陰葉 日当たりの悪いところに 陰葉ができ、葉はうすい ⑤ 光合成と植物の形態 P20. 植物の種類によって葉の形態や重なり方が異なっている。⇒光合成による物質生産と関係深い。 ダイズ畑⇒広い葉が上層部を覆い多くの光を受け取り、下層部では、光合成量に差がある 永田ヲイネの細長い葉が斜めなので、下層部に光がさし込み、上層部から下層部まで全体に葉が多い →ダイズ畑と比べると、上層部と下層部で光合成量の差は小さい P20 図8 光 ダイズ イ 光
ページ5:
Blate 第1章 生物と光 ② ⑥ 植物の発芽と光 P22 【発芽に光が必要な植物がある。 例タバコ、レタスなどの種子→光発芽種子という。地表が明るい場合のみ発芽 光発芽種子の発芽に有効な光→赤色光である。→有効な波長→660㎜mo 遠赤色光(730mm)は発芽の抑制 植物が生育している→赤色光を吸収する→地震に落ちた種子発芽は抑制 赤色光の効果 遠赤色光を当てる⇒打ち消される。 両方の色を交互に当てる照らした光で発芽するかしないか決まる ⑦植物の成長と光 P22. Q.当が光たらないと植物の成長はどうなるか? もやし→ヤエナリなどの種子を暗所で発芽させて育てたもの。 →種子が土の中で発芽した時、芽が地表に出るまで、 茎はもやしのように細長く速く成長 ⇒種子中のエネルギー源であるデンプン、脂肪が枯渇する前に、 日の当たるところに出る反応。 芽が地表に出て光が当たる→茎はゆっくりと伸長し、緑の葉を広げる・P22図10 図10 a明所 b.暗所.. ⑧ 植物の成長運動と光 P22. 自然界の地面に落ちた種子は温度が適度になり、水分供給 発芽 発芽した植物→光などの刺激で一定の反応を示しながら成長。 刺激源に対して一定方向へ屈曲する性質→屈性という。 刺激源のほうへ屈曲する場合、正の屈性といい、 反対に屈曲する場合、魚の屈性 + 光が当たらない側の茎の細胞が光の当たる側の細胞よりも成長する。 細胞,器官の不均等へ運動→成長運動 によって生じる
ページ6:
⑨花芽の形成と光 P231_! 「花になる芽 花芽という。多くの植物→決まった季節に開花。 花芽形成が日長(昼の長さ)の変化を強く受けている。 ← a 長植物 春から夏にかけて日長が長くなる時期に開花 例コムギ、アブラナ、ホウレンソウ、カーネーション b 短日植物→夏から秋にかけて日長が短くなる時期に開花 例イネ、キク、ダイズ,アサガオ、コスモス C 中性植物+眼長に無関係 例トマト、トウモロコシ、セイヨウタンポポ Ⅰ 花芽形成のしくみ P23 「明期をいう光のあたる期間と暗期という真っ暗な期間の長さを人工的に変えたり、 暗期の途中で光を短時間照射したりして、花芽形成の有無が分かる。 (1) 花芽形成に重要なのは、明期の長さよりも連続した暗期の長さである。 (2)短日植物は連続した暗期が一定時間より短いと花芽形成する。 [花芽を形成するかしないかの境界となる音期の長さ→限界暗期 Ⅱ 長日処理と短日処理 P24 日産 夜間、植物体に人工的に光を照射して連続した暗期を短くする→長日処理 夕方や朝に植物体を遮光するなどして暗期を長くする→短日処理 例 キク→夏の早い時期から短日処理をする→開花を早める。 秋に長日処理を行って花芽形成を遅らせ、一定時期に処理を止める 正月ごろに開花。(カーネーションも同じ)→温室で行う。 B ヒトの視覚と光 P25 私たち→眼、耳の感覚器官を通じて、環境からの刺激を受け取り、 環境の変化で行動。眼は光を刺激する器官。 眼の網膜には光に反応する感覚細胞が並んでいる。 10. 光や音、におい, 味を感じるが、環境について極めて多くの情報を与えるのが視覚
ページ7:
①眼の構造とはたらき P25~P27 眼の構造=カメラ例 カメラ 絞りの役割=こう彩を開閉して調節。 フィルムの役割=網膜(視細胞があり、光の受容)⇒無意識に感度を変えられる。 凸レンズの役割=水晶体(光線屈折させて網膜上に像を結ぶ) ヒト→水晶体の厚さを変えて光の曲かりを変えて遠近調節の役割 ピントを合わす役割=近点。近点と水晶体の距離→近点距離 ヒトの網膜は2種類の視細胞がある 1 明るい場所で色に反応する錐体細胞 2 薄暗い場所で明暗に反応する桿体細胞である。 網膜の中心部 黄色に見える→黄斑とよばれるが、錐体細胞が多い。 網膜の周辺→桿体細胞が多い。 明るい場所→暗い場所に入る初め最っ暗で何も見えないが、やがて慣れて見える ⇒暗順応 暗い場所→明るい場所に入る初めまぶしいが、桿体細胞の感度低下し、ふつうに見える。 1 明順応 網膜には、視神経が集まって眼球から出る→盲斑(光は感じられない)。 P25 図15 ヒトの眼の構造(見づらいと思います!)はその場所 物体→ 光線 ⑨ ④ ① 14) ◎① 角膜(かくまく) ◎②重要水晶体(すいしょうたい)→厚さの変化で遠近調節する ②③チン小帯(チンしょうたい) ④ ガラス体(ガラスたい) ⑤重要網膜(もうまく) ⑥脈絡膜(みゃくらくまく) ⑦強膜 (ごうまく) ⑧ 血管(けっかん) ⑨ 視神経(ししんけい) ⑩ 盲斑(もうはん) P25図16. ◎①重要黄斑(おうはん)→錐体細胞が多く集まっている ②重要毛様体(もうようたい)→水晶体の厚さの調節 ◎13 重要 こう彩(こうさい)→光量を調節する。 ◎14瞳孔 (どうこう) (ひとみ
ページ8:
赤色光 期期末メモ P22 図9. 1タスの種子の発芽に見られる赤色光と遠赤色光の効果 赤色 赤色光 赤色光 四遠赤色光 光を照射する 順序 ○ 遠赤色光 ○□○□ 遠赤色光 ○□□□/////←遠赤色光 25 結論(P22図9から) Date ( 一発芽率 50 75 「赤色光の効果はその直後に遠赤色光を照射すると打ち消し。 両方の光を交互に照射すると、最後に照射した光によって 発芽するかしないかが決まる。 最後 赤色光 発芽率が高い。→70%を超える。 遠赤色光→発芽率が低い。→10%を切る。 気になる Word ☆1P233 ・・・強く受けているためである。の部分。 L 生物が日長の変化に応じて一定の反応を示す性質→光周性 k2P23l13... 短時間照射したりして、花芽形成の…の部分。 - 4暗期の途中で、短時間、光を照射すると暗期の効果が失われることがある。 暗期の効果を失わせる光照射光中断 1 P25 el 感覚器官の部分。 →一定の形をもち、特定の機能を営む体の部分器官 その中で感覚機能をもつ器官が感覚器官 3 P25 ell (デジタルカメラの場合は撮像素子)の部分。 光を電気信号に変換する素子
ページ9:
側面 P25 図16. 近くの物体を見るとき 遠くの物体を見るとき こう彩 ・毛様体 * 光線 「光線 水晶体 水晶体 チン小帯 正面 ・水晶体 網膜 毛様体の筋肉が収縮する時水晶体が厚い。 近くのものを見ることが出来る。 こう彩を除いた 近点にピントを合わせたとき、筋肉は最も強く収縮している。 状態
ページ10:
Date 第1章 生物と光 ①P30 9/13(木) C 動物の行動と光 P31 1. 光に対する動物の反応 P31. 1.刺激源に向かったり、逆に逃げたりする動物の行動⇒走性 光に対する走性 光走性。刺激源に向かう走性→正の走性 刺激源から遠ざかるのを負の走性。 例 ガンガゼ(ウニの仲間)負の光走性体の上に影が落ちると、それに反応してとげを振り動かす。 →陰影反射。 反射 刺源に対して無意識に神経を介して一定の反応が起こる現象 ※アマガエル、カメレオン、コウイカ、ヒラメ⇒周りの色や明るさに応じて体の色や明るさ、模様を変える動物 もあり、これらの体色変化には神経などがかかっている。 背景に合わせて目立たないように体色変化させることが多い 3 概日リズムと体内時計 P34 基本昼に行動する動物 一定の周期で繰り返す 昼行性動物(例ヒト) 活動のリズム→生物リズム 夜に行動する動物→夜行性動物(例 フクロウ)) 生物リズムのうち、光や温度などの環境条件に関わらず維持され、ほぼ24時間の周期で 繰り返すリズムを概日リズム(サーカディアンリズム)という。概日、ほぼ1という意味 多くの動物 光のない暗黒中に置かれても、ほぼ旧周期の活動のリズムを示す。 →> 周期は24時間ぴったりではなく、ヒトのように長いものや、ハマダラカのように短いものもいる。 Ⅰ 体内時計 P35 生物体内一定のリズムを保つしくみがある。⇒体内時計(生物時計)と呼び、 代表的なものが概日リズムをつくり出すものである。 これについては、ヒト・ショウジョウバエ・ゴキブリなど調べられており、共通のしくみ 4 ヒトの健康と光 P35 P36. Ⅰ 光と体内時計 P35 ヒトの概日リズムの時計は約25時間であるが、毎朝、光を浴びるごとに「時計」の「時刻合わせ」が 起こる。ヒトは、昼行性の動物であり、体温は夜より昼のほうが高いなど、 体内の環境も昼の方が活動しやすい。 毎日、朝日を浴びて、外界の昼と生物リズムの昼とがずれないようにする。 体内時計は、昼夜の時間と同期できないので、飛行機を使って短時間で時差の大きい場所へ 移動すると、昼に眠くなり、強い疲労を感じる。時差ぼけ
ページ11:
II 光によるビタミンDの合成 P35-P36 「ビタミンDは骨をつくる上で重要な働きをする物質である。 骨のカルシウムの沈着の促進し、腸からのカルシウム吸収の促進。 乳幼児期にビタミンDが不足すると、骨格の発達に異常を生じ、くる病になる。 成人でも不足すると骨粗しょう症になる。 ビタミンDは魚類やシイタケの食品から摂取できるが、体内でも合成される ビタミンDの合成が起こるには、皮ふが紫外線に当たる必要がある⇒日光が当たらないとビタミンDの不足 II 紫外線による健康への影響 P36 紫外線に当たりすぎると、日焼けや角膜炎を起こすことがある。 紫外線を眼に大量に浴びた時も、急性の角膜炎を起こすことがある。 慢性傷害問題になる皮ふがんである。紫外線は皮ふの細胞のDNAを変化させることがあり、 変化ががんの原因。眼の慢性傷障 白内障がある。水晶体が濁るため、 対象がぼやけたりして見える病気。 紫外線は波長によってUV-A, UV-B, UV-Cに分けられる。 UV-A→地表に達するが、健康には有害ではない。 UV-Cのほとんどは大気の層により吸収。 UV-B → オゾン層などにより吸収されるが、一部は地表に達し、影響を及す 20世紀中ごろ冷蔵庫やクーラー、スプレー缶に使用されたフロン→オゾン層の破壊作用あり。
ページ12:
No. 授ノート P42図6と書いている所 == Date 第2章 微生物とその利用 ① P389/14(金) A微生物の存在 P38 1 微生物とは P38 肉眼では見えず、顕微鏡を使用して初めてその生物がわかる生物→微生物 最古の微生物の化石→約35億年前の地層で見つかっている。 微生物には、ヒトに害を及ぼす病原体がいる→人間生活に欠かせない。 1例1 ヒトの腸内にいる微生物や例2食品あるいは医薬品の生産に役立つ微生物である。 2 微生物の仲間 P38 微生物には、細菌類や、菌類、原生生物 ①などが含まれる。→分類学的には微生物という区分はない 分類学では、生物は大きさではなく、形態や生殖の仕方で分類。 ◎肉眼で見えるものと見えないものが、分類上は同じ仲間に属するものもある。 例 クロレラが属している原生生物に、ワカメやコンブのような生物も属している。 ◎肉眼では見えない生物を一まとめにして微生物という。 ①の説明 細菌類┬細胞内に核をもっていない生物 原核生物・原生生物 I' 一細胞内に核をもつ生物→真核生物 L菌類、動物、植物以外- 3 微生物の発見の歴史 P41~P44 i 微生物の発見 P41 1674年 オランダのレーウェンフックは自作の顕微鏡を使って初めて微生物の発見。 レーヴェンフックは倍率が約200倍の単レンズ顕微鏡を用いて様々な微生物の観察後、 ビールの中の酵母菌についても報告。 ii 自然発生説の否定 P42 レーウェンフックが微生物を発見した17世紀においても、「生物は親なしに無生物から自然に発生する」 自然発生説が信じられた。19世紀フランスのパスツールは(授業ノート参照)自然発生説を否定 「生物は生物から生じる」ことが科学的に正しくなった。 パスツール→ブドウ果汁がワイにならず酸っぱくなってしまうことがある 酵母菌によるアルコール発酵が進まず乳酸菌の繁殖してしまうから。 良質なワインを造るための低温殺菌法(パスツーリゼーション)の開発。
ページ13:
[ii] 病原体の発見 P43 → ドイツのコッホは固形培地をペトリ皿に作り、これを用いて様々な細菌を培養、分離の成功 1876年に炭疽菌が炭疽の病原菌であることが明らか。 結核菌、コレラ菌の発見。 多くの研究者が病原体となる微生物の発見→感染症の原因究明が進んだ。 微生物は17世紀にレーウェンフックによって発見されたが、ウイルスは細菌類や菌類よりも 大きさが小さいので、20世紀まで確認できなかった。 1890年 ロシアのイワノフスキーにより、タバコモバイル病の病原体について、素焼きの陶板を使って大きさを調べた。 未焼きの陶板には、極めて小さい穴が開いている→大腸菌や赤痢菌などの細菌は穴の通り抜けは できない→3液には病原体がなかった。 しかし、タバコモバイル病の病原体の含む水 3液に病原性が認められた。 ← ろ過性の病原体であるウイルスの発見 ← 1931年ドイツのルスからによって発明された電子顕微鏡に観察方法の進歩 ウイルスの確認 iv 病原性微生物との闘い P44 病原性微生物による感染症 人類は甚大な被害を受けた。 -> 例 インフルエンザ、エイズ、SARS、結核など。人間は、治療法の開発など医学の進歩により、 感染症と闘っている。この闘いは終わってはいない。 4 食中毒と微生物 P45 「母体内の胎児の腸の中→無菌 生後まもなく多数の微生物がすみつく。 →消化・吸収を助けたり、ビタミンをつくり出すものもいる。また、体外から侵入する微生物の 増殖の阻止 感染防止に役立つものもいる。 食中毒 食品と一緒に体内に入ったサルモネラ菌や病原性大腸菌などにより起こる 感染型食中毒と、黄色ブドウ球菌やポツリヌス菌などが食品中で増殖してつくった 毒素により起こる毒素型食中毒がある。 B 生態系における微生物 P46 多くの細菌類や菌類は落葉や生物の遺体・排出物の有機物を分解し、分解者の役割を 果たす。 生物とその周り環境を一まとまりとして捉えたもの→生態系→生産者は二酸化炭素や アンモニウムイオンを取り入れ、炭水化物やタンパク質などの有機物をつくる。→消費者に利用 生産者や消費者の遺体、排出物に含まれる炭水化物やタンパク質は、分解者として働く微生物に 利用。炭水化物→二酸化炭素や水など、タンパク質→二酸化炭素・水アンモニウムイオンに分解後、 生産者に利用。有機物を構成する炭素は、生態系内を絶えず循環しており、それによって全ての生物と 環境がつながる。この循環の中で微生物は分解者として大きな役割を果たす。 1.生態系と微生物 146
ページ14:
2 水の浄化と微生物 P48 河川においても有機物などを含む汚水流入すると、量が少ない内は大量の水で希釈されたり、 微生物が分解したりすることなど→有機物による水の汚染は改善 自然浄化 家庭や工場の排水、家畜の排出物などが大量に河川や湖沼に流出→再染が広がる。 防ぐために... 家庭・工場排水は、河川や湖沼に流れる前に人工的に処理され、浄化される。 排水の処理の一つとして、好気性微生物によって有機物を水と二酸化炭素に分解する 活性汚泥法がある。細菌や原生生物などが繁殖して塊を形成したもの=活性汚泥である。 活性汚泥を排水に加え、空気を送り込むと、活性汚泥中の生物が水中の有機物を分解 活性汚泥は塊となって沈殿するので、その上の澄んだ水を川へ流す。 汚泥の一部は活性汚泥として再利用し、残りは肥料に使用。
其他搜尋結果
推薦筆記
瀏覽紀錄
中1 理科 用語まとめ
8
0
與本筆記相關的問題
Senior High
生物
2番と3番がなぜこの結果になるか教えて欲しいです。解説読んでも分かりませんでした。
Senior High
生物
問1の問題の答えがなぜ石英なのですか? わかる方いらっしゃいますか?
Senior High
生物
(3)教えてください
Senior High
生物
全然わかりません😭教えて欲しいです
Senior High
生物
呼吸はなんでエネルギーが2回もできるんですか?
Senior High
生物
⑹の問題についてなんですが、答えがA.C.DなのですがAが入る理由を教えてください
Senior High
生物
34,35の答えを教えてください🙏
Senior High
生物
有機物の記号がこうなるのはなぜですか?普通に暗記ですか?
Senior High
生物
動物細胞と植物細胞の呼吸でエネルギーが2回できるとおもうんですけど、なにがちがうんですか?1回目にできたエネルギーはすべて、ATPがADPとPに変わるので使われてしまうのですか?
Senior High
生物
図を参考に空欄に当てはまる言葉教えてください🙏🏻 既に埋めてあるところも間違ってたら教えてほしいです
News






















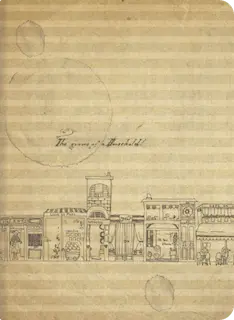
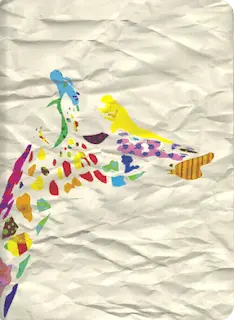

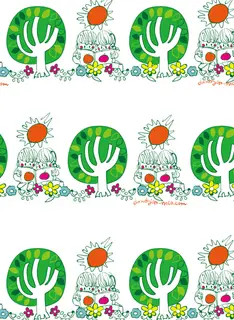

留言
尚未有留言