ノートテキスト
ページ1:
平安時代前期代表哥 日本の最古の日記文学 高知県から京へ帰る日記 土佐守に就任 No. Date 土佐日記 紀貫之 男もするらしい日記をせもしようとしてするのだ。 男はする日記といふものを、せもしてみむ 27 すなるして書く F 伝推 オニが出入りするち を んなもじ V La:& F 東 e する 女性仮話 真名をとこもじ 仮名をんなもじ 南十年 the 亥 Ft 某年の十二月の平日の午後八時頃 に出たいぬ 西 それの年の十二月の二十日余り一日の日の戌の時その年、甘木年・ある年 そういう訳で、その旅について少し書きつける。 戌の時…午後らへん 乾岬( けんこんいて に、門出す。そのよし、いささかにものに書きつく 門出す旅に出る 理由 ある人がとする四五年を終えて国守交替の いささか少し ある人 県の四年五年果てて、例のことどもみなし 県の四年五年・国守とし 紀貫之隴化表現・ぼかす 地方に勤務する四・五年 例のことでも…国守交替の 意訳 ときのきまり も終えて、公文書を取官ちから出て、港へ移動 終くて、解由など取りて、住む館より出でて、船 した。)船に乗るはずの場所へ行ったあの人この人、つきあいがある人も に乗るべき所へわたる。かれこれ、知る ← ら ときのきまり 解由…新作が仕者 の任務宗を証明する 住む館・・・国守の官舎 (今の高知県南国市江 船に乗るべき所…今の高 大津にあった考
ページ2:
年ごろ長年 日ごろ数ヵ月間 日ごろ 数日間 つき合いがない人も見送りをする。長い間よく親しくつきあっていた人々と別れ 送りす。年ごろよくくらべつる人々なむ、別れが くらべると交際 完 してきた 年ごろ…長年 たくないと思って毎日とにかくさわぐうちに夜が更けた たく思ひて、日しきりにとかくしつつののしるうち 反復 日しきり とかく・・・あれやこれか ののしる大声でさわぐ に、夜更け 3 はつかあまりっかいずみ 二十二日に和の国が無事にたどりつくように神に祈かん <二十二日に〈和泉の国までと、平らかに願立つ。 和の国…大阪府南部 せめて無事であるように 藤原のときは船の通 にいるけど、送別のうたげをする。 平らかに願立つ であるように神に祈る 藤原のときの船路れど、むまのはなむけす。 海 むのはなむけ…立つ 人への花むけの言葉が金品 馬の自向け かみなかしも 身分の高い者も低い者もうんざりするほど酔っぱらってたいよう奇妙なこと しおうみ 上中下、酔ひ飽きて、いとあやしく、潮海のほと 飽く十分満足 () に腐るはずのない海のほとりでふざけ合っている。 にて、あざれ合への。 あざりけた。 宗3 ている T に E E E E E E L L T 7
ページ3:
No. Date 二十五日 八木のやすのりという人がいる。 この人はみず はっかあまりみや 今二十三木のやすのりといふ人あり。 八木のやすのり 仕事を言いつけて使う人ではないようだ。 国に必ずしも言ひ使う者にもあら 国の役所 C ざるなりだ(ん)なり 音便の無表記化 は立派な様子で花むけの花をした。 たたはしきやうにそむまのはなむけしたる たたはしきいかしく 様子 係り結び 宗体 よかったから 国の人であろうか、 かみがら その国の人の心の習いとして、「今は」と見送り 守柄あらむ国人の心の常として、 「 守柄…土佐守の人柄 心理的な 結び らしいが、 にかってこない にある者は恥じずに来てくれる。 伝 優しさまごころ・正義 www 別の原因 二十四日。 とて見えなると、ある者は、恥ずにな これはものによってほめるわけではない。 来 ある これはものによりてほむるにしもあらず はつかあまりよかことじ 打消 国分寺の僧侶は旅立ちの花むけにおいでになった。 <二十四講師むまのはなむけに出でませの wwww 国分寺の僧侶。 講師 尊敬宗の教えを講じる者
ページ4:
さえ 低い人、子どもまでもが酔っぱらってしまって、一文字 ありとあらゆる身分の高い 12. ありとある上・下、童まで酔ひしいて、 「文字を www 痴る ちりあし ↑ さえ知らない者は、その足は十文字に踏んで遊んでいる。 m だに知ら煮 しが足は十文字に踏めて遊ぶしが足には、その兄は
ページ5:
帰京 家に着いて門に入って目が明るいので 京の町中に入っていくのでうれしい。 京に入り立ちてうれし。家に至りて、門に入るに Date 入っていく 京に入り立ちて 一月 三十日に和泉の国に苦 淀川を上って二月十六日の 京へ入った。 とてもよく様子が見える。 月明ければ、いとよくありさま見 聞いたよりもまさって 聞きしよりも 順の確定 見える 直接過去作 ☆家が壊れていた ことがないほどこぼれている。 家だけでなく預けておいた まして、ふかひなくぞこぼれ破れたる家に預けたり家に預けたりつる人のにも 3 宗3 存続 ・・・家だけでなく預けてお いた留守番の人の心も、 留守番の人のも荒れていたのだ。(なぁ) 中垣があるのに つる人の心も、苦れたるはり 中垣こをあれ 中垣隔での垣根 2wx 宗作 断定 過去 丼屋に 先方向から) 一つの家のようなので望んで預かったのだ。 それでも私は 一つ家のやうなれば、望みて預かれる ~なので こんなことはない。 何かあるごとに品物をあげていたのだ。 たよりごとにものも絶 使 貫えが と、大声で身内や家来たちに文句を言わせない。 今夜「このようなこと。 よい 今宵 かかる 家が荒れ果 てていた 情だと 」と声高にものも言はせいとはつらく 大句 使 吉高に大声で www 尊
ページ6:
No. は思うが、お礼はしようと思う。⇒不満はあるが、大人げないから。 見 とす こころざしはせ 量 さて、次のようにくぼんで水がたまっている所がある。ほとりには松 さて、池めいてくぼまり、水つける所あり。ほとりに ①管理が悪いため池とは言えない 池のことを司る ②けんそん表現 存続 もあった。 五・六年のうちに千年が過ぎ ちとせしまったのだろうか、 松もありき。五年六年のうちに千年過ぎたむ 過去 松の一部分がなくなってしまっている。 お松には最近生えたものが混じっている かたへはなくなり 、今生ひたるぞ混じれる 宗3 過去 ほとんど枯れてしまっているので、「ああ。ひどい。」と人々はいう。 →3体 おほたかみな苦れれば、「あはれ。」とぞ人々 おほかた…ほとんど 過去 思い出さないこともなく、恋しく思っているうちにこの家で生まれた ふ。 思ひ出でことなく、思ひ恋しきがうちに、 女の子が一緒に土佐から帰ってこないので、どんなに悲しいことか。 この家に生まれ〇女子の、もろともに帰られば 消 順の確定
ページ7:
Date 人もみんな、子が寄り集まって騒いでいる。 いかがは悲しき。人もみなみたかりてののしる 大喜び 船人同じ船で一緒に 帰京した人々 そうしているうちに、非悲しみにたえられなくてひそかにの通った人 かかるうちに、なほ悲しきに堪へして、ひそかに 言った歌 と言った。 3 休 生まれても帰らない子供を思いながらわが家に 生まれも帰らぬものをわが宿に ☆松は成長するが子供は死んでしまっているため成長しない ある小松を見るとよりいっそう悲しくなるなぁ 小松のあるを見るが悲しき まだ満足しないのであろうか、またこのように書いた。 ののしる大でさわぐ かかるうちにそうしている うちに と言くる。ほか⑥やあら またかくなむ www このように かつて見た人が 結びの省略 中が松の千年が見ることができるならば 見人の松の千年に見ましかば 反実仮想未 見し人ここは、七きせ のこと
ページ8:
永遠に悲しい別れをしただろうか、いやしなかっただろう。 遠く非ごしき別れせまし 反実仮想 れられず、残念なことが多いけれど、書き尽くせない。 忘れがたく、くちをしきこと多かれど、え尽く す くちごを残念 www L 消 なこと 本当は破ってない とにかく、こんな日記はさっさと破ってしまおう。 とまれかうまれ、とく破りてい ともかく れ 宗木量強意+意志 確述用法 →とまいかうまれ
留言
登入並留言其他搜尋結果
推薦筆記
與本筆記相關的問題
Senior High
古文
古文の羅生門についてなのですが 「そこで洛中のさびれ方はひととおりではない。」 というところの解説をお願いしたいです。
Senior High
古文
古文単語の「こちたし」は仰々しい。という意味で、おおげさな感じなのかなと捉えていたのですが、「ところせし」の意味にもおおげさだ。という意味があり、どうやって使い分けるのですか?🙏🏻
Senior High
古文
問三の②なぜタリ活用になるんですか、?
Senior High
古文
高校一年生、古文の文法問題です。 写真の⑵の答えが「ざ 連体形」になるのですが、その理由がわかりません… 「めり」は終止形接続だから「ず 終止形」になると思っていました。 どなたか解説お願いします🙇
Senior High
古文
高校一年生、古文の文法問題です。 写真の問題の答えが ⑴ざる ⑵ず ⑶ざら (4)ざれ (5)ざり (6)ず になるのですが、その理由がわかりません… どなたか解説お願いします🙇
Senior High
古文
高校一年生、古文の文法問題です。 写真の⑵の答えが「さする」(「さす」の連体形)になるのですが、その理由がわかりません… どなたか解説お願いします🙇か
Senior High
古文
古文の問題で質問です。 行成大納言の額、兼行が書ける扉、あざやかに見ゆるぞあはれなる。 という文の「あざやかに」の活用形を答える問題で、答えは連用形となります。 連用形になる理由は分かるのですが、この文には「ぞ」 が含まれていて、「ぞ」は係り結びであるため、連体形にもなり得るのではないかなと思いました。 他にも例は挙げられませんが、「こそ」が含まれている文なのに活用形が已然形ではないものもよく見かけます。 係り結びが含まれる文の連体形、已然形になる場合、そうでない場合の違いを教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
Senior High
古文
答えがなくて困っています。 このテキストの6-9、14-17、18-21の答えがあったり分かったりすれば教えて欲しいです。
Senior High
古文
古文で質問があります。 活用の種類や活用形、こきくくるくれここよ みたいな言葉は覚えたんですけど使い方や判断の仕方がよく分かりません。 1枚目や2枚目の写真はどうやって判断しているんですか?覚え方やコツがあったら教えて頂きたいです。 テストが近いのでよろしくお願いします。
Senior High
古文
古文の助動詞「き・けり」の範囲です カ変「来」 →未然形「こ」+し/しか →連用形「き」+し/しか らしいのですが、「こ」+し/しかと「き」+し/しかの違いはなんですか? ただ、言いにくいから変わった版もあるし、そのままのもあるよーってだけなのでしょうか? サ変が サ変「す」 →未然形「せ」+し/しか →連用形「し」+き とあったため、なぜサ変は言いにくい版はないのに、カ変はあるのかと疑問に思ったため質問させていただきました🙇
News












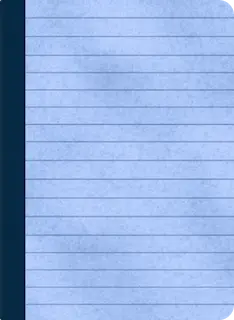
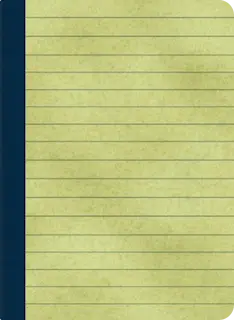



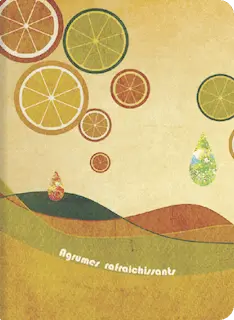

コメント失礼します🙇♀️ペンの色分けを何でしているか教えて欲しいです!よろしくお願いします!