Undergraduate
看護
重症頭部外傷
3
325
0
今後の投稿予定(順不同)
心不全
急性大動脈解離
急性呼吸不全、ARDS•••人工呼吸管理も含めて
痙攣重積発作•••ER
高エネルギー外傷関連(致死的胸部外傷、腹部外傷、骨盤骨折など)
オーバードーズ
DKA
高/低K血症•••ER
セプシス
呼吸療法認定士の試験内容の復習•••呼吸生理、酸素療法、酸塩基平衡など

ノートテキスト
ページ1:
頭部外傷 (traumatic brain injury:TBI) ※重症のみまとめ
ページ2:
1.病態と治療の概要 病態 外傷による頭部外傷のうちGCS<8と定義され、 頭蓋内圧 (ICP) 亢進を認め重篤な状態となる ・脳の循環障害や代謝障害などの二次性脳障害によって脳浮腫や脳虚血が引き起こされる 超急性期 一次性脳損傷 : 外傷によって脳実質の損傷を引き起こす 損傷した脳実質は治療は困難 治療 急性期 ・二次性脳損傷:一次性に引き続きする浮腫などにより脳虚血など生じた結果 頭蓋内圧亢進、 脳幹圧迫、 脳循環不全を引き起こす TBI治療はこれらを改善・予防するのが主体 ・線溶系異常: TBI後の凝固線溶系により出血傾向となり 頭蓋内血腫が増大する可能性あり PS・SC: ①ABCDE評価・安定化 ② 出血コントロール ICU・HCU:① 頭蓋内圧管理 ② 呼吸循環状態の安定 ③ 感染対策 ④全身状態の改善
ページ3:
2.重症度分類と 「切迫するD」 判定基準 表4 頭部外傷の重症度と意識レベル 重症TBIの定義: GCSスコア8以下(JCS100以上に相当する) GCSスコア 重症 3~8 中等症 9~12 JCS スコア 100~300 10~30 GCS<8は脳ヘルニア徴候のある 「切迫するD」 の判断にも用いられる 判定基準のうちいずれか該当すれば 「切迫するD」である 軽症 13~15 0~3 「切迫するD」の判定基準 ① GCS <8・・・E/V/Mの合計点が8点以下の場合 ②経過中にGCS合計が2点以上低下・・・ 受傷後72時間以内に起こる進行性意識障害 T&D(talk and deteriorate) という ③脳ヘルニア徴候を伴う意識障害・・瞳孔不同、 除脳・除皮質硬直、Cushing現象など Cushing現象 bICP亢進時のB上昇と徐脈 除脳硬直 除皮質硬直
ページ4:
3.TBIの分類 びまん性脳損傷(DBI) ~脳虚血、脳血管損傷、 脳腫脹、 びまん性軸索損傷などを含めた広範囲にわたる脳損傷 ・局所性脳損傷(FBI) 脳挫傷、硬膜外血腫、 硬膜下血腫、 脳内・脳室内血腫など局所に限局した損傷 硬膜下血腫などはICP亢進を伴い、 脳ヘルニアを生じるリスクがある これらが併存することも多い
ページ5:
4.Primary Survey (PS) ①Airway: 気道確保と頸部の保護 気道閉塞や意識障害がある場合、 頸椎損傷を考慮し下顎挙上法で気道確保する。 必要なら挿管準備 ②Breathing : 呼吸管理、 低酸素血症の予防 酸素投与や人工呼吸を行い低酸素血症を防ぐのが重要 リザーバーマスクで酸素流量MAXで速やかに投与。 事前にリザーバーを膨らませておく SpO2>95%が目標 ③Circulation: 循環管理、 循環血液量減少の評価 出血性ショックによる脳血流減少を防ぐ リンゲル液などの輸液を行いSBP > 120mmHgを維持。Hbは10g/dL以上を維持 末梢循環評価はCRT (毛細血管再充満時間)、冷汗、皮膚温の確認で行う 頭部以外からの出血を見逃さないため医師によってFASTが行われる ④ Dysfunction~ : 意識レベルの評価 GCS<8や脳ヘルニア徴候があれば 「切迫するD」 として直ちに頭部CT施行 ⑤ Exposure~ : 体温管理 処置時の脱衣や初期輸液などで体温は下がる傾向にある シバリング誘発や感染リスク、 薬物代謝能などの観点から望ましくない。 TBIへの低体温療法のエビデンスはない シバリングはICP亢進を起こすリスクあり避けなければならない 輸液は39℃に加温するのが望ましい
ページ6:
5.Secondly Survey (SS) ① 「切迫するD」 を認めた場合、直ちに頭部CTを行う ~頭蓋骨骨折、出血、脳浮腫、正中偏位(midline shift)の有無を確認 ②CT後の処置 ・頭部挙上: 静脈灌流を促しICP下げる ・マンニトール投与浸透圧利尿でICP下げる ペッダの眼 バトルサイン ・ICPモニタリング : BP<90、 GCS<8、 midline shiftありの場合 ③詳細な身体診察 ・瞳孔所見…径、 直接・間接対光反射、 瞳孔不同 (アニソコ)の有無を経時的に観察 ・ICP亢進症状・・・ 悪心・嘔吐、頭痛、 意識レベル低下、 BP上昇 (脈圧拡大) と徐脈 ・その他…前頭蓋底骨折ではパンダの眼徴候や髄液鼻漏を、 側頭骨骨折ではバトルサインなどを認めるため併せて観察する 漏出した体液が髄液かどうかの判定方法はダブルリングテスト (右記画像) 頭皮の創部や全身観察を行う ・受傷機転の詳細な問診・・・意識障害がない場合に実施 受傷の背景に低血糖や不整脈などがある場合あり 一髄液 血液成分
ページ7:
5.二次性脳損傷の治療 ①原因:/(1)占拠性病変・・・ 硬膜下血腫や脳内出血による脳損 頭蓋内 因子 (2)脳ヘルニア・・・脳幹圧迫による (3) 脳虚血…脳ヘルニアなどでICP亢進し脳灌流圧(CPP) 低下や脳血流量(CBF)低下による虚血で組織低酸素状態 (4)脳浮腫…細胞毒性や血管性の脳浮腫 (5)痙攣…組織低酸素状態となる \(6) 感染…炎症性サイトカインなどによる直接的な傷害、またサイトカインがDICを惹起しMODSへ移行する /(7) 低酸素血症…組織低酸素 (9) 貧血…DO2(酸素運搬能)低下 頭蓋外 (8)低血圧…低灌流 因子 (10) 高熱…代謝亢進により酸素需要増大し供給低下 (11) 高・低CO2血症…pH変化が生じ、 脳血管径の変動を起こしICP亢進や脳虚血になりうる。 低CO2で脳血管拡張 ②治療: (1)(2) 血腫除去 内減圧・外減圧 (後述)髄液ドレナージによるICPコントロール、 止血術 (3)ICPコントロール、 CBF低下あるならMAPやPaO2 PaCO2是正。 CPP: 60~70mmHg、MAP: 90mmHg以上 (4)電解質補正(低Naなど)、抗浮腫薬(マンニトールなど) (5) 抗痙攣薬 (6)抗菌薬、創部保護、 ドレーンやカテーテル類などの感染対策 (7) 酸素投与、人工呼吸管理 (8)輸液、昇圧剤、血管作動薬 (9)輸血 (10)解熱剤、クーリング、 熱源精査 ICPモニタリングをすることで予後改善効果あり ・ICP:22mmHg以上は予後不良 22以下での管理が推奨されている。 (11)人工呼吸器設定変更、 低換気原因の除去、頻呼吸の原因精査 (高度侵襲によりSIRS→ARDSに進展しているなど)
ページ8:
6.各病態と治療 ①頭蓋骨骨折: 骨折部位などによって分類される • 分類:(i)部位別 ・円蓋部(頭蓋冠) 骨折・・・急性硬膜外血腫や硬膜下血腫、 脳挫傷などを招く ・頭蓋底骨折・・・髄液漏、髄膜炎、 視神経損傷、 脳血管損傷などを招く (ii) 外部との交通性別 頭蓋冠骨折 頭蓋底骨折 頭皮 開放性・・・感染リスク高いため硬膜縫合などの手術適応 ・閉鎖性・・・保存的治療 骨 開放性骨折 閉鎖性骨折 (骨と外部の交通あり) (骨と外部の交通なし) ・症状:・円蓋部骨折・・・ 頭蓋内血腫を伴うと意識障害、 片麻痺、 ICP亢進症状 ・頭蓋底骨折・・・前頭蓋底 パンダ眼徴候、 鼻出血、 気脳症、 視神経障害 中頭蓋底→バトル徴候、 耳出血、 気脳症、 顔面神経麻痺 後頭蓋底→頸部や咽頭部の出血斑、 稀に脳幹損傷による呼吸抑制 緊張性気脳症 頭蓋内 の空気 空気による 脳の圧迫 ・治療:円蓋部骨折・・・開放性陥没骨折では骨片や異物除去後に頭蓋形成術 血腫に対して開頭血腫除去や外減圧術など(詳細は次項参照) ・頭蓋底骨折・・基本的には保存的治療 一方的な 空気の流入 損傷した くも膜 ●瘻孔部のくも膜が弁となり,一方的に空 気が流入し続ける. 頭蓋内圧が上昇し, 脳が圧迫される. 髄液漏がある場合は頭部挙上し逆行性髄膜炎を予防する。 鼻腔や外耳をタンポンなどで詰めるのは厳禁 気脳症は自然治癒するが、稀に緊張性気脳症となり脳ヘルニアをきたすことがあるのでICP亢進症に注意
ページ9:
② 急性頭蓋内血腫 (1)急性硬膜外血腫 外傷による中硬膜動脈などの損傷で頭蓋骨と硬膜間に出血が生じる 受傷側の出血が多い 頭部CT像で凸レンズ型が特徴。midline shiftも認める 頭蓋骨と硬膜が密に結合しているため血腫が広がりにくく比較的予後良好 時間経過とともに硬膜が剥離すると脳ヘルニアに進展するリスクあり 緊急の開頭血腫除去術が必要 骨と硬膜の 間に出血 骨 硬膜 くも膜 血腫の厚さが1~2cm、 血腫量が20~30mL以上、 合併血腫の存在時に行う (2)急性硬膜下血腫 : 硬膜下腔の出血。 脳動脈や架橋静脈の破綻で生じる 受傷部位と反対側に三日月型の出血を認める 硬膜とくも膜の結合は弱く、 血腫が広がりやすく予後不良 受傷直後から急速に意識レベル低下する 緊急の開頭血腫除去術・ 止血術を行う 一頭皮 ・帽状腱膜 一骨膜 架橋 静脈 の断裂 ・骨 血腫の厚さが1cm以上の場合 出血部位 (硬膜下腔) 適応 意識障害を呈し正中偏位が5mm以上ある場合 明らかな mass effect (圧迫所見) がある場合 血腫による神経症状を呈している場合 神経症状が急速に進行する場合 8888888888 硬膜 脳表 ・上矢状静脈洞 硬膜 くも膜 くも膜下腔 くも膜 動脈 一軟膜 脳実質 (3) 脳挫傷: 頭部外傷により脳の挫滅、 小出血などをきたした状態 対側損傷として生じることが多い 血腫や浮腫による脳の圧迫 (mass effect) の程度で保存的治療か開頭術が決定される 進行性の神経症状悪化、 ICPコントロール不良で挫傷脳除去や血腫除去術を行う
ページ10:
③ びまん性軸索損傷 交通外傷などで生じる回転加速度衝撃によって、 脳の神経線維断裂をきたした病態 CT像で出血や脳腫脹などは認めないが、 持続する意識障害を呈する 治療法がなく保存的治療が原則となる 高次脳機能障害を残すことが多い 予後不良で過半数が死亡、 1/3が植物状態となる 回転加速度 組織境界部 速い」 外力 00 ••••• 遅い ●回転速度の違いにより 神経組織が断裂する. 7.合併症 ・凝固線溶系異常: 重症TBIの急性期に生じることが多いとされる 脳挫傷や硬膜下血腫など局所性脳実質損傷による組織因子放出が凝固・線溶亢進を招くなどが原因とされる その結果、線溶を抑制する因子が枯渇し出血傾向となる 高齢者でより多く起こりうる 確立した治療法はないが、 FFP (新鮮凍結血漿) 投与やトラネキサム酸 (止血剤)投与が有効という研究結果もある
ページ11:
8.その他 ・外減圧とは ~開頭血腫除去術後に行う処置 術後の脳浮腫が予想される場合に、開頭術時に切除した頭蓋骨の一部を戻さないまま保護し圧の逃げ道を作る その部位に外圧がかからないよう体位変換など注意が必要 外減圧術 ・内減圧とは 受傷した脳の一部を切除し、 頭蓋内の容積を減らすことでICP減圧を図る術式 重度の脳浮腫が生じている場合は外減圧ではなく内減圧が行われる 内減圧術 皮膚が伸びて 圧を逃がす 頭蓋内容積 を減らす
其他搜尋結果
與本筆記相關的問題
News















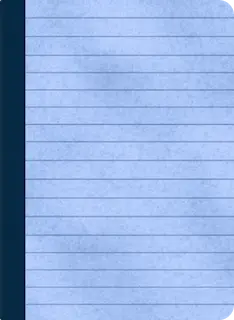
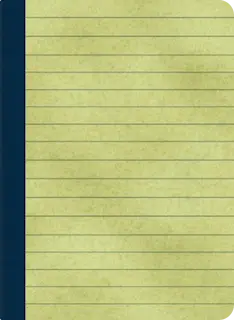

留言
尚未有留言