ノートテキスト
ページ1:
鎮痛薬 青 P.211 ~ 1148 鎮痛薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。 2つ選べ。 雨の○デュロキセチンは、選択的にセロトニン及びノルアドレナリンの遊離を抑制し、糖尿病 阻害 刺激 モルヒネ 性神経障害に伴う疼痛を改善する。 2タペンタドールは、麻薬に指定されている鎮痛薬であり、オピオイド受容体を刺激し て上行性痛覚伝導路を抑制する。 3 ペチジンは、鎮痙作用を示すとともに、オピオイドル 受容体を遮断して鎮痛作用も示す。 4 ペンタゾシンは、オピオイド受容体に対する完全刺激作用とオピオイドに受容体に対 する部分刺激作用を有し、モルヒネよりも強力な鎮痛作用を示す。 Q5 プレガバリンは、神経細胞内のCa"濃度を減少させ、興奮性神経伝達物質の遊離を抑制 して鎮痛作用を示す。 ◆memo◆ ☆細胞内にCaが増えると伝達物質↑。(膵Bcell→インスリン、血小板→ADPなど) 下行性抑制系 下行性痛覚抑制系 セロトニン トランス (ポーター α2受容体 ノルアドレナリン (5-HT) [NAd) ノトランスポーター トラマドール 5-HT NAd トラマドール △△ △ グルタミン酸、 サブスタンスP等 e 電位依存性Ca2+チャネル 1 ←トラマドール モルヒネ プレガバリント Gi) サブユニット 上行性痛覚伝導系 強オピオイド 絶対出る ☆モルヒネより強い薬 タペンタドール 赤→強オピオイド ・フェンタニル ・オキシコドン ・ブプレノルフィン MR刺激 (NAd取り込み阻害 のみ! 比較トラマドール(非麻薬→弱オピオイド) - MR刺激 -20- NAd5HT 取り込み阻害
ページ2:
☆酸性度の問題=共役塩基の安定性を考える。 ☆電気陰性度大=共鳴を起こしやすい。 H3C-CN 1 H2C-CEN 共鳴〇 H3C-COCH3 2 H2C-COH →O水素の酸性度=ケトン>エステル(2.5比較) H3C-C6H5 3 回 共鳴△ Spa H3C-CH3 4 H3C-CH2 #X :NH2 SP3 H3C-CO2CH3 〇が共鳴を邪魔する HC 5 NO2 .N. L -P -N: SP₂ 1 2 P軌道=塩基性X ☆塩基性度=Nの電子密度を考える。 Spa> Sp2 > Sp 3 5 ローンペア× 共鳴してしまうため. 塩基性X ☆ 共役酸の安定性を考える。 -16- 2 共鳴するため共役酸は 安定! SP2より塩基性
ページ3:
基質 2級 弱塩基、イオン・・・ 求核性大 H Br HS H3C. HS H CH3 CH3OH B Hac CH₂ SN2 (立体反転) R →SN2 ☆2級+求核性 ☆E2は強塩基で起こしやすい。 Q9. H OSO2 CF HaC CH3 ☆SN1では基質濃度のみで進行が決まるが SN2では基質と同期両方関与。 中途半端な2級+強い試薬はSN2優 ★試薬がH2Sの場合は中間体が 作りやすくなるため、SN1が優先される。 ☆脱離基は外れた後に安定 なら反応性が大(共鳴安定) -CF3 Q10.PMF=非プロトン性 -0- トリフルオロメタン スルホン酸アニオン (H3C)3C (H3C)C D Br 強塩基 NaOCH2CH3 Br CH2CH2OH E2脱離 Todacto ☆脱離基をアキシアル位へ。→anti脱離 単一のエナンチオマー=Rのみ、Sのみ CH3C)3 CR (鏡) ラセミ体 手前 (HC)CS
ページ4:
(4) モバルビタールは、以下の反応で合成される。本合成に用いられる化合物A及びB はどれか。 2つ選べ。 1) NaOC2H5. C2H5OH H 2) CH3CH2Br 3) NaOC2H5, C2H5OH H3C A 5) B 4) (CH) 2CHCH2CH2Br NaOC2H5, C2H5OH H3C NH H3C アモバルビタール H3C CH3 H3C OC2H5 C2H5O OC2H5 2 3 4 1 H & H3C-CEN H3C NH2 H₂N NH2 NH2 8 7 6 5 <医薬品の合成> O 登場人物をCHECK. 気にしなくてOK 17NaOCzHls C2H5OH(強塩基)基本的にアルコキシドを使う時は同じC数の 2) CH2CH2(Br (ハロゲン化ヒアルキル)←SN2 と予想が立てられる。 4) (CH3)=CHCHCHB(ハロゲン化ヒアルキル) アルコールを一緒に使う。 H3C HIC NH H3C. 0 ☆反応した場所を予想→α位のC→選択肢から1.2.3.4 pick. (両側のC=0) ☆1.2.3.4をCHECK NHは存在しない(置き換えられる部分を見つける) LOCHSはと、Nに置き換わる事ができる。 OC2H5はとれやすく、Nに置き換わる事ができる。 ☆上の他の残りの部分を考える H2N Ni NH2) -41-
ページ5:
HCO. CH3 O HN H3C H H H3C H H HO F ソホスプビル 酵素 HN [HHC HO F A H ウラシル HN OH OOHOO 酵素 HO 1.ほとんどのL-アミノ酸はS配置 (L-システインはR配置)を持っているため、 2.Aでは水溶性が上がっている(取り込み×) ソホスブビルは細胞内に入って活性化する。 3.ヌクレオシド=核酸塩基+糖 ヌクレオチド ☆逆に覚えてたから注意!! 核酸塩基+糖+リン酸 <HHC H H HOF 活性代謝物
ページ6:
H2NH CH3 HOCOH CH3 H CO₂K H -OH H H HO アモキシシリン クラブラン酸カリウム Q6. トランスペプチダーゼ(セリン残基) アミル化 6 トランスペプキダーゼ 8- NHO トランスペプチダーゼ HNI 8+ R:アルキル基 Ben 求核置換 アミド pQ=アシル基 エステラーゼが届きにくくなる。 HO H3C CH3 H3CH3C CH3 H3CH₂C CH3 H3C CH3 HC- CH3 H3C CH3 H3C' ~CH 3 H3C ~CH3 アセチルコリン Sメタコリン -メタコリン ムスカリン Q12. マーカーを付けたの隣のが同じ形の方が結合しやすいと考える。 CH3 -CH3 H3C + CH3 水素結合 イオン結合 (立体) ☆アクセプター(受容体)=Hを受け取る方。 ☆ドナー(供与体)=Hを与える方。 57- HIC CH3 CH3
ページ7:
●直接滴定と逆滴定 直接滴定 標準液の消費量 本試験>空試験 逆滴定 第二標準液の消費量 本試験<空試験 <本試験> < 本試験 > 誤差 医薬品 医薬品 誤差 第一標準液 の余り 標準液 <空試験> 第一標準液 誤差 医薬品なし 第二標準液 <空試験> 標準液 誤差 医薬品なし 第一標準液の余り 第一標準液 これがあると逆商定確定! 第二標準液 見分け方 過量の過剰の遊離した●●●を◆◆◆で滴定」と記載があったら逆滴定 本試験と空試験を両方行う目的 二酸化炭素の影響などによる誤差を補正するため Bmolで反応する = ★Amol ●対応量 ☆ 〇mol1 molル 標準液1ml=□mg薬(分子量M 標準液1mLに対応する試料の量(mg)のこと。これに、定量によって求められる標準液の消費量(mL) とファクターを乗じることにより、 試料の量 (mg) を計算する。 反応する医薬品のモル数 対応量= ・ 標準液の濃度 × 医薬品の分子量 反応する標準液のモル数 BA 右 * 左 x端×端
ページ8:
急性疾患 慢性疾患 性病(CKD) ループス 胃炎 ** 急性糸球体胃炎 溶連菌感染後腎炎 硬化症 アミロイドーシズ 多発性膿胞 慢性糸球体炎血尿タンパク 急性不全 IBANE 小変化 ステロイド有効 実質性腎不全 「薬剤性腎症 巣状分節性糸球体硬化症 メサンギウム増殖性胃炎 膜性腎症 ステロイド効果 (シクロスポリンを用いる) ★ネフローゼ症候群 原因 好発 盂腎炎(上部尿路感染) 慢性骨不全 定 血液浄化療法 (透析) 膀胱炎(下部尿路感染) 単純性の場合は大腸菌 複雑性の場合には緑膿菌やクレブシエラによる上行感染 単純性は若い女性に、複雑性は高齢者に起こりやすい 症状 治療 発熱、腰背部痛、血尿 混濁尿、頻尿、排尿痛、残尿感 ・飲水を促進して多尿状態にする ・抗菌薬(ニューキノロン系、ペニシリン系、セフェム系)の投与 分類 シュウ酸カルシウム 特徴 尿路結石の中で最も多い リン酸カルシウム 要因 : 高シュウ酸尿、高カルシウム家、酸性尿 一成分はまれ . 要因 高カルシウム血症、アルガ リン酸マグネシウムアンモニウム . 要因 : 路染症(ウレアーゼ産生菌の感染、アルカリ 酸性尿 GooD ブロテウス菌感染に続発する。 プロテウス菌はウレアー ゼ活性をもっており、尿素を分解してアンモニアを産生し 尿を通常よりさらにアルカリ性にする 要因 高尿酸血症、尿酸排泄促進薬、酸性 尿酸 アルカリ尿 GOOD 予防 アルカリ化薬(クエン酸製剤) . 金属を含まないため、X線透過石である(写らない) シスチン 硬質で遺伝性がある アルカリに溶けやすい ※高カルシウム駅を起こす! 製品:アセタゾラミド、活性型ビタミンD、製剤などは、カルシウム結石の リスクを上昇させる。
ページ9:
☆甲状腺H=代謝up↑ ☆TRHはTSHとプロラクチンの分泌を制御! ☆内分泌疾患:甲状腺と副腎疾患をCHECK! ★甲状腺キノウ低下症と副腎皮質キノウ不全合併患者 先に甲状腺Hを補充すると、副腎皮質Hの代謝↑ →副腎キノウ不全(副腎クリーゼ) ① 副腎皮質H ② 甲状腺 H ●順番で補充する!
ページ10:
アロプリノール:キノウ抵下で投与量調整 通常、成人は1日量アロプリノールとして200~300mgを2~3回に分けて食後に経口投与する。 年齢、症状により増減する。 機能 Cer50mL/分 30mL/分ter 50L/分 Cor80mL/分 血液透析行例 腹膜透析施行例 アロプリノール投与量 100~300ng/日 100ng/ 50mg/日 終了時に100ng 50mg/日 重度の障害の場合には、フェブキソスタットは慎重に投与する。 アロプリノールが腎が悪いと使えないから改良したフェブキリスタットができた! ☆★クレアチニンクリアランスにより用量を変更する薬物 アログリプチン シタグリプチン アマンタジン ベザフィブラート ファモチジン ダビガトラン レボフロキサシン アロプリノール
ページ11:
<P製剤まとめ>☆P.65 参 ★シスプラチン(第一世代)=副作用大 改善 4 (: 高度催吐性リスク ・腎毒性大←投与前後に輸液を併用 (必要に応じて利尿剤使用) (輸液も利確も不要! 必須ではない ★オキサリプラチン(第世代) 副作用小 ★カルボプラチン(第世代)
ページ12:
ミセル形成の過程 ☆ミセルを形成する濃度=C.m.c温度・クラフト点 ii !! 単体 (モノマー) 80 ミセル CITIC d P 水 88X クラフト点以上で ミセル形成可能 ●界面活性剤溶液の性質の濃度による変化]疎水:(アルキル基)鎖が長くなる=ミセル形成↑↑ 界面活性剤溶液の性質 洗浄力 可溶化力 (難溶性物質の溶解度) 「浸透圧] 表面張力] 「当電気伝導度」 cmc 界面活性剤濃度 (N) ラムダ ★当量:1mol当たりの ★電気伝導度(K)は 濃度が上がれば上がる。 親水基:(イオン形の部分):水にとけやすくなりミセル形成↓↓ "1 しやすさ=非イオン界>イオン形界 ☆ミセル形成する濃度=c.m.c ☆池セル形成しやすい=c.m.c↓↓(非イオン形) しにくい=com.c↑↑(イオン形) <温度について> ☆クラフト点:イオン性界面活性剤の溶解度が急にup↑↑ ミセルを形成できる。 ☆曇点・非イオン性界面活性剤の溶解度が急にdown ◎の親水基がまわりと水素結合してとけている。 温度が上がると水素結合が切れて白濁する。(2本) 乳化作用 ミセルは不要(可溶化はミセルが必要) ☆HLB (H2O Love Balance) (基準=7) 1・HLB大=親水性 →0/m型 Bancroft ° HLB⑩=疎水性に親団性)→w/型 経験則
ความคิดเห็น
ล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสรุปนี้
Senior High
数学
なぜy➕2ではなくy-2なのか、わかりませんでした。教えてください。
Senior High
数学
「2」の問題は両辺をn(n +1)で割る解き方をすると解説にはあったんですが、なんでそんな解き方をすると解けるってわかるんですか?式を見て見抜けるものなんですか?
Senior High
数学
1枚目の写真の(1)の問題で2つの解と書いてあるのに、D>0ではなく、D=>0になっているのはどうしてなんでしょうか。お願いします🙇♀️
Senior High
数学
上の式に2分の3をかけるんですが、下の式になりません。計算の途中式を教えてください。🙏
Senior High
数学
赤の線引いてるところがわからないです!
Senior High
数学
なぜ|x|≧5の解はX≦−5,5≦Xになるのですか? (Xより5の方が大きいんじゃないですかね?) もうそういうものなのですか?
Senior High
数学
何も考えずに積分して間違ってしまいました この問題を解くときの考え方と解き方を教えていただきたいです
Senior High
数学
数学の微分積分の分野の面積を求める問題について質問です。 写真のように、解説にマーカー部分のような記述があったのですが、こんな表現をしてる問題集を私は見たことがなかったので、模試や試験本番でもこんな書き方していいのかな、、と思ったのですが、こんな書き方をしても減点されたりしませんか?? 教えてください🙏 お願いします!
Senior High
数学
①の上の式から①の式にするやり方がわからないです。わかる方お願いします🙇♀️🤲🤲
Senior High
数学
⑵をどうやってとくかを教えていただきたいです。 よろしくお願いします!
News

















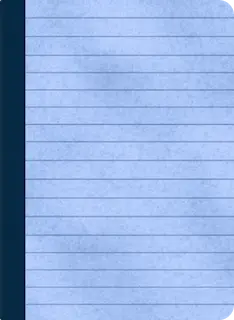
ちょwww
分かりやすすぎwww
初日とりあえずお疲れ様でした!いつも参考にさせて頂いています。フォローしても宜しいでしょうか。