ノートテキスト
ページ1:
Date P112 篆刻 EP →石などの卵材に文字を刻して卵を作ること 名称 立 → 干支印 年賀状に押す三中・住所印 成語印 好きな言葉を倒した 姓名印→名前を刻した卵 左下に押印する 一般的に正方形 雅号印 関防印 →本名以外の別名を刻す 姓名印と組み合わせて用いることがある 左下に押印、正方形が多い →→好きな言葉や、心境を戻した語句を刻す 右上に押印、長方形が一般的 印の種類 ° 白文印→文字が白くなる 姓名印は白文が多い 朱文印→文字が赤くなる、雅号印は朱文が多い 篆刻に必要な用具 (P113左下) 印刀 印泥、印床、印材、印矩 仮名について 万葉仮名 まがな おのこで →別名真仮名・男手 奈良時代に広まった 主に楷書と行書で書かれた
ページ2:
No. Date 変体仮名 ※ →平仮名とは字源が異なったり、 字源は同じでも、くずし方の異なる仮名 表現の変化や調和という効果をもたらす P72,73を見て勉強して下さい 連綿→文字を続けて書くこと 連綿線→文字と文字をつなぐ線のこと 形連→連綿が美線でつながった場合 つながっていないが、単派の通っている場 ↓ 意連→ 形連と意連の組み合わせによって、美しい流動美 が生まれる 連綿の法則 (P74) 形連 ①上と下の文字の 中心がそろう ②下の文字を 右に寄せる ③上の文字の終筆と 下の文字の筆を 重ねる 意連 ① 上下の文字の 筆派を通して書く ※P74を見て 勉強して下さい
ページ3:
No. Date 様 構成の工夫(P100) ①行頭 行末 →行頭や行末をそろえたり、 変化をつけたりする ②行の傾き →行や語句の 御に角度をつける ③文字の大小文字の大きさに変化をつける ④文字群と余白 →余白とのバランスを取りながら、 文字群を構成 散らし書き (P82) 各行の長短や高低、頂きに変化をつけたり、 行間の広さに差をつけたりすることによって、 余白とのバランスを図りながら、文字群を構成する 表現技法 著作権 (P97) 文化的な創作物が持つ権利のことで、 著作権法で保護されている 作品を複製したり、素材として書作品にする場合、 著作権を持つものの了解が必要である ※授業では自由に使用可能 著作権が保護される期間(日本) →作者の死後五十年間
ページ4:
Date P112 篆刻 EP →石などの卵材に文字を刻して卵を作ること 名称 立 → 干支印 年賀状に押す三中・住所印 成語印 好きな言葉を倒した 姓名印→名前を刻した卵 左下に押印する 一般的に正方形 雅号印 関防印 →本名以外の別名を刻す 姓名印と組み合わせて用いることがある 左下に押印、正方形が多い →→好きな言葉や、心境を戻した語句を刻す 右上に押印、長方形が一般的 印の種類 ° 白文印→文字が白くなる 姓名印は白文が多い 朱文印→文字が赤くなる、雅号印は朱文が多い 篆刻に必要な用具 (P113左下) 印刀 印泥、印床、印材、印矩 仮名について 万葉仮名 まがな おのこで →別名真仮名・男手 奈良時代に広まった 主に楷書と行書で書かれた
ページ5:
No. Date 草仮名 平安時代 漢字の草書を 用いて書かれた仮名のこと 仮名 →別名 女手 平安時代中期に草仮名をさらに簡略化 したもの ※このように漢字を徐々に簡略化したものが平仮名 片仮名→漢字の一部分から考え出されたもの 片仮名の字源 伊→イ 井→牛 保→ホ →キ 奴→又手→ヲ 由 →ユーサ→メ須のス 平仮名→1900(明治三十三年に一音一字 に整理された 平仮名 の 字源(P70) 以 9 n 波→は 仁→に 保つほ 部→へ 止っと 知→ち 利→り 留 → る 遠つを → 和→わ 加→か 奴→ぬ 与→よ 太った 礼れ買っそ 川→つ 袮→ね 奈→な 良→ら 武→む 宇 墨継ぎ → 仮名を書くときには、一度墨をつけたら、 二、三文字を書く。その後、途中で墨を つけることを墨継ぎという 墨継ぎにより、潤湯の変化や強弱や 立体感が生まれる
ページ6:
No. Date 変体仮名 ※ →平仮名とは字源が異なったり、 字源は同じでも、くずし方の異なる仮名 表現の変化や調和という効果をもたらす P72,73を見て勉強して下さい 連綿→文字を続けて書くこと 連綿線→文字と文字をつなぐ線のこと 形連→連綿が美線でつながった場合 つながっていないが、単派の通っている場 ↓ 意連→ 形連と意連の組み合わせによって、美しい流動美 が生まれる 連綿の法則 (P74) 形連 ①上と下の文字の 中心がそろう ②下の文字を 右に寄せる ③上の文字の終筆と 下の文字の筆を 重ねる 意連 ① 上下の文字の 筆派を通して書く ※P74を見て 勉強して下さい
ページ7:
No. Date 様 構成の工夫(P100) ①行頭 行末 →行頭や行末をそろえたり、 変化をつけたりする ②行の傾き →行や語句の 御に角度をつける ③文字の大小文字の大きさに変化をつける ④文字群と余白 →余白とのバランスを取りながら、 文字群を構成 散らし書き (P82) 各行の長短や高低、頂きに変化をつけたり、 行間の広さに差をつけたりすることによって、 余白とのバランスを図りながら、文字群を構成する 表現技法 著作権 (P97) 文化的な創作物が持つ権利のことで、 著作権法で保護されている 作品を複製したり、素材として書作品にする場合、 著作権を持つものの了解が必要である ※授業では自由に使用可能 著作権が保護される期間(日本) →作者の死後五十年間
ประวัติการเข้าดู
テスト勉強方法
19
0
คำถามที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสรุปนี้
Senior High
芸術・作品
書道の授業で座右の銘を書くのですが、私の座右の銘は「塵も積もれば山となる」で長いから私には書けません🥲 なので!!書きやすいことわざとか教えてください🙇🏻♀️🙇🏻♀️出来れば似た意味の言葉を教えて欲しいです!
Senior High
芸術・作品
美術で「ものを持つ手」についてデッサンをしているのですが、感想が思いつかないです。私は、定規を持った手を描いています。このプリントにある項目にあった感想の例やどんなことを書くのかを教えてくださると嬉しいです。お願いします。
Senior High
芸術・作品
美術で「物を持つ手」をデッサンしていて、私は定規を持った手を描いたのですが、感想を何を書けばいいかがわからないです。何を書けばいいのか、例などを教えてくださるとありがたいです。
Senior High
芸術・作品
美術で「ものを持つ手」のデッサンを行い、私は定規を持った手を描いたのですが、感想プリントに何を書けばいいのかがわからないです。どうゆうことを書くのか、例などを教えてくださるとありがたいです。
Senior High
芸術・作品
音楽なんですけど、( )の中に入る音階を教えて欲しいです。
Senior High
芸術・作品
至急です。音楽の和音の展開を教えて欲しいです。 写真の上の段を例に下の2つを和音展開して欲しいです。
Senior High
芸術・作品
質問です。ピカソの作品ゲルニカの材質、技法についてですが、油彩とキャンバスという認識でしたが、この他にもあると言われました。材質、技法として何が足りないのかが知りたいです。わかる方教えていただけると嬉しいです。
Senior High
芸術・作品
部活のポスターで書いたんですけどどういう配色にしたらいいのか本当にわかりません😭😭 メインは緑色で塗りたいんですけどカメラの丸い部分の1番外ふちはこの色で~っとか具体的に教えてほしいです。
Senior High
芸術・作品
高校2年生です。 高校の行事として研究発表が2学期中に行われるので、研究内容を考えているのですが、割とマジめに、かつ欲を言えば聞き手が興味惹かれる、面白そうと思えるような研究内容が思いつきません。どなたか研究内容を発案していただけませんか? 自分の取り組む研究テーマは心理学です。心理学に関係するものだったらなんでもいいです。いいなと思った案にベストアンサーさせていただきます!
Senior High
芸術・作品
高2の美術1です! 西洋美術の問題です! ①~④の答えが分かる人は教えて下さい! 宜しくお願いします!
News











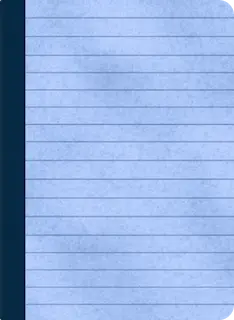

ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น