✨ Jawaban Terbaik ✨
まず、モル濃度には2種類ありますね。
①質量モル濃度と②(体積)モル濃度
①②共に電離を考えますが、①は希薄溶液の沸点、凝固点を考える時に使用します。
この時、沸点・凝固点は①に比例します。だから電解質の場合、電離のモル合計で考えます。
それ以外の計算では、②を使います。単独の②計算では、電離まで考えませんが、中和の計算では価数が必要になるし、浸透圧の計算では、①同様、電解質ならイオン合計のモルに比例します。
以上より、
①も②も電離を考慮するが、単純なモル濃度計算だけなら考慮しない。①は沸点上昇・凝固点降下にか出てこないが、②は中和、浸透圧計算では価数、イオン合計を考える🙇
①②が、どんな時に、何の計算を、何のために、行うとどうなるかを再読し、比較されることをお奨めいたします🙇
再度補足します。
①も②も電離を考慮しますが、単独の濃度計算では考慮しません。
①は、高校では、希薄溶液の濃度でモル沸点上昇・モル凝固点降下を使った計算にだけ使うから、①だけ使うと思われているかもしれませんが、その勉強の後に浸透圧の勉強が出てきます。
その場合は②を使いますが、その時に電解質なら、①同様イオン合計を考慮し計算します。
中和は水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度を合わせる反応で、ここでは全モル数ではありませんが価数という言い方にしてますが、それを合わせるようにしています。
②が電離を考慮しないのではなく、電離を考慮しない分野で多く使用する。①は使用場所が少ないが、全て考慮している。それだけの違い。
最後、沸点上昇・凝固点降下を考えるのに②を使わず、①を使うのは、温度により②は変化するため。詳しくはラウールの法則を学習されて下さい。
②は、毎回言っていませんが、25℃での計算を考えています。ただ、浸透圧計算では、温度が25℃でないことが多いから、ファントホッフの浸透圧計算の式に入れて計算します🙇
長くなりました。以上です🙇














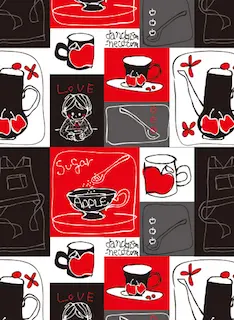


ありがとうございます!ちゃんと再読しようと思います!