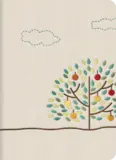Chemistry
SMA
(4)でSO2やNOが酸化力を示さないのはなぜですか。
それと、(6)でNOも酸性雨の原因になると思ったのですがなぜ該当しないのか教えて頂き
たいです。よろしくお願い致します。
(2)
でも
195 〈気体の製法と性質〉 ★★ 4/7
次の(ア)~(コ)の組み合せにより発生する気体について, 下の(1)~(7)の問いに答えよ。
(7)亜鉛と希硫酸(b)(イ) 硫化鉄(II)と希塩酸(ウ)炭酸カルシウムと希塩酸
(エ)塩化アンモニウムと水酸化カルシウム(オ)酸化マンガン(IV)と濃塩酸
(ク) 銅と希硝酸
(カ)銅と濃硫酸)(キ)銅と濃硝酸(ク) 銅と希硝酸
(ケ) 水素化カルシウム (CaH2) と水
(コ)過酸化ナトリウム (Na2O2) と水
(1) 水上置換で捕集すべき気体のうち、最も軽い気体を発生する組合せ(2つ)
(2) 発生する気体が水に溶けて塩基性を示す組合せ (1つ) ()
(3) 気体を発生させるのに, 加熱が必要である組合せ (3つ)
4)発生する気体が水で湿らせたヨウ化カリウムデンプン紙を青変させる組合せ (2
2) OnMicha
0.0
(5) 発生する気体が酸性を示し、反応が酸化還元反応でない組合せ (2つ)用
(6)発生する気体が濃硫酸では乾燥できない組合せ(2つ)
d7) 酸性雨の原因物質と考えられる気体が発生する組合せ (2つ) (工学院大改)
なので、
酸のうち
性の強さたん
Mにヒド
いる。
酸)
陽性が
が大きく
OHE
強くなり
生が強
0-H
る。つら
場合、
くなり
→0
す。
巨大
HO-S-OH
[参考
オキソ酸MO (OH), の酸性の強さ
O
↑
HO-S-OH <
亜硫酸(弱酸)
O
硫酸 (強酸)
O=N-OH
<
亜硝酸(弱酸)
O=N-OH
硝酸 (強酸)
中心原子 M と OH との結合は単結合 (M-OH)
であるが,MとOとの結合は, 二重結合 (M=O)
または配位結合 (MO)である。
MOではM原子から0原子へ非共有電
子対が提供されており, Mの電気的陽性が強
くなるため, O-H結合の極性が大きくなりH+
が電離しやすくなる(酸性が強くなる)。また,
M=OでもO原子がM原子との共有電子対を強
く引き寄せるので, Mの電気的陽性が強くな
あるため, O-H 結合の極性も大きくなり,H+が
電離しやすくなる。
一般に, オキソ酸MO (OH)では,中心原子
Mの陰性が強いほど,その酸性が強くなる。
また,Mが同種ならば,Mに直接結合した
原子の数(k) が多くなるほど, オキソ酸の酸性
は強くなる。
これに対して, M に結合した-OHの数は、
オキソ酸の酸性の強さにはほとんど影響しない
-OHの数(Z) が多くなるほど,Mの電気的
陽性を弱めるので, オキソ酸の酸性はかえって
弱くなる傾向を示す。
195 (1) (ア) () () () () () () ()
() () () () (),(ウ) (6)() ()
(7)(カ), (キ)
解説 (ア) Zn+H2SO4ZnSO+H
(イ) FeS+2HCI → FeCl + HS↑
←中性
((ウ) CaCO3+2HCI→ CaCl2+H2O + CO2↑
(エ) 2NHCl+Ca (OH) 2CaCl2+2NH3↑+2H2O
(オ) MnO2+4HCI → MnCl2+2H2O+Cl2)
CuSO +2H2O +SO2↑
(カ) Cu+2H2SO
til
(キ) Cu+4HNO
Cu(NO3)2 +2NO2↑ +2H2O 1
(ク) 3Cu+8HNO33Cu(NO3)2 +2NO ↑+4H2O
(コ) 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑
参考
(ケ) CaH2+2H2O→Ca (OH)2+2H21 中性
(NO)
過酸化ナトリウムと水の反応
過酸化ナトリウムNa2O2 は, 過酸化物イオン
(-O-O-) と Naからなるイオン結晶である。
・希酸や冷水との反応では, 過酸化水素を生じ
る。
NaO2 + 2HCI → 2NaCl + H2O ...... ①
NaO2 +2H2O→2NaOH + H2O2...... ②
常温の水との反応では、過酸化水素がさらに
分解して酸素を発生する。
2H2O2→2HO+O ...... ③
・よって, 過酸化ナトリウムと常温の水との反
応式は、次の通りである。
13 非金属とその化合物 135
②×2+ ③ より
2Na2O2 + 2H2O → 4NaOH + O2
(1) 水上置換で捕集するのは,水に溶けにくい H2,
O2およびNOで,これらのうち最も軽い気体はH20
水素化カルシウム CaH2 は Ca2+と水素化物イオン
2Hからなるイオン結晶である。 水との反応では,
Hと水中のH+ とが結合して H2 が発生し, Ca²+と
水中のOHからCa (OH) 2 が生成する。
(2) 水溶液が塩基性を示す気体は,高校段階では
NH だけと覚えておけばよい。
(3) 加熱が必要な反応は, (エ) 固体と固体を反応さ
せる,(オ) MnO2の酸化剤としての働きを強める
(カ) 濃硫酸 (不揮発性, 酸化剤, 脱水剤の働き) を使
用する反応の場合である。
(4) ヨウ化カリウムデンプン紙を青変させるのは
酸化力をもつ気体で, Cl2, NO2, Og が該当する。
/NO2 は水に溶けてHNO3 となり酸化力を示す。
\Cl2 も水に溶けてHCIOとなり酸化力を示す。
(5) 酸性の気体は, H2S, CO2, Cl2, SO2, NO2 で
ある。 (イ), (ウ) は (弱酸の塩) + (強酸) (強酸
の塩) + (弱酸)で表される酸塩基の反応である。
(ア), (オ), (ケ), (コ)のように,化合物→ 単体, ま
たは単体化合物の形式の反応は, すべて酸化還
元反応である。 () () () のように, 金属と酸化
力をもつ酸との反応も、酸化還元反応である。
(6) 塩基性の気体のNH3 の乾燥に、酸性の乾燥剤
(H2SO4) を用いると, 中和反応が起こり気体が吸収
されてしまうので不適である。 また,還元力の強い
H2Sを濃硫酸に通じると, 常温であってもH2Sが酸
化されてSを遊離してしまうので不適である。 (SO2
は濃硫酸と酸化還元反応を起こしH2SO4 に酸化さ
れるが,同時に H2SO4 が還元されて SO2 が再生さ
れるので使用できる。)
(7) 石油や石炭の燃焼で生じた硫黄酸化物 (SO) や
自動車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(NO)
が,大気中の酸素や水などと反応して硫酸や硝酸と
なり、酸性雨が生じるとされている。
196(1) (ア) 17 (イ)7 (ウ) 電子親和力
(工) 1 (オ)共有 (カ)高 (キ) フッ化水素
(ク) 高
(2) (a) MnO2+4HCIMnCl2+Cl2+2H2O
(b) Ca (CIO) 2H2O +4HCI
|→ CaCl2+2Cl2 ↑+4H2O
(c) 2F+2H2O→4HF+O
(d) Cl2+H2OHCI + HCIO
(e) CaF2+HSO, CaSO,+2HF↑
(f) SiO2 +6HF→H2SiF+2H2O
(g) NaCl+H2SO4NaHSO+HCI
(3)(b)
Answers
No answer yet
Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?
Pengguna yang melihat pertanyaan ini
juga melihat pertanyaan-pertanyaan ini 😉