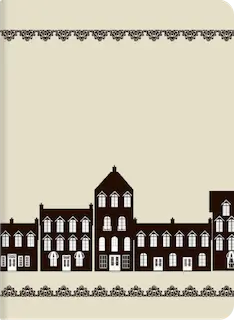Contemporary writings
SMA
高2の現代文です。『擬似群集の時代』で、写真の四角で囲んである「この特徴」は何を指しているか分かりません💦お願いします教えてください🙏🙏(2枚目が1つ前のページです)
いとき、必ずしもそれは消極的な意見を表しているのではないのかもしれない。それこそ
が擬似群衆に特有の態度であるかもしれない。
S
のような特徴を潜在させてレンズの前に立ち現れる人間たちは、かつてとは違った装
いをしているのだろうか。歴史上さまざまな群衆が記録されてきたが、ポスト情報化社会
を形成する最大の群衆は、目に見えないのではないか。それを一言で表すならば、「待機
する群衆」ではないかと思う。都市だけではない。地球上のどこにいても、情報システム
を通じてつながっている群衆は、常に何かを待っている。たとえば労働の場において、非
正規社員や移民労働者の不当解雇が世界規模の問題となっているが、それは見方を変える
と、常に待機することを余儀なくされる人々が爆発的に増大しているということではない
かと思うのである。
てのひら
彼女や彼は、掌の小さな画面を見つめながら、何かを待っている。待つ群衆がいかなる
力を潜在させているのか、それが見えてくるかどうかは、芸術にとっても政治にとっても、
無視のできないテーマになるであろう。
5
5
ている、さまざまなコミュニティを想
ように言葉を介している場合もあれば、オンラインゲームのようにアクションの共有に
よって形成されている群衆もある。
トを
投稿し
するこ
ビス。
いる。
りょうが
こうした実空間では互いに隔離されているのに、情報空間では互いに影響を与えられ
る具体的な関係を持っている擬似的な群衆が、 実在の群衆を凌駕してしまうという現実 ~
である。これはお茶の間でテレビの前に座っている間に形成されている、視聴者という名
の群衆とは明らかに異なる性格のものだ。それは物理的な建築を必要としない、新しい都
市であり、どこにも場所を持たないが、あらゆるところに存在しているとも言える空間で
ある。私たちが生きる都市とは、この空間と絶え間のないイメージ交換によって成立して
もう一つは、非決定性の増大と仮に呼ぶことができるだろう。かつてなかったほどの多
くの情報チャンネルを持った個人は、意思の決定を先延ばしにする傾向がある。 それは必
ずしも、待ち合わせの場所をあらかじめ決めないというような、単なる習慣の変化ではな
い。残されている時間がある限り、より多くの情報を手にしつつ、最後の瞬間まで心を決
めない。決定しない群衆が、購買から投票までさまざまな局面において、影響を増してい B
くのではないか。たとえば選挙に関するアンケートで「分からない」と回答する比率が多
*
5
端的
擬似
メリカ
0111
を変更
隔離
Answers
No answer yet
Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?
Pengguna yang melihat pertanyaan ini
juga melihat pertanyaan-pertanyaan ini 😉