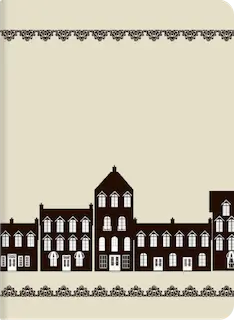全体として、筆者の主張が小難しい表現で一般人にはわかりにくい表現となっています。
そうであれば、筆者は具体例を用いて私たちに説明しようとしてくるはずです。具体例をよく読んでそこから、筆者の主張を類推するしかありません。
そのことを裏付けるが如く、この文章は異常に具体例を丁寧に書いています。
筆者が具体例として出しているのは、ブラジルのビシャゾンとして描かれた言葉の元ネタが松尾芭蕉の言葉であったことについてです。
芭蕉の句は春をモチーフにしていますが、ブラジルにおいて描かれた芭蕉の句と日本で書かれた芭蕉の句ではその表現するものが異なるのです。
また、レミンスキーが引用したポルトガル語で訳された芭蕉の句も具体例として出されています。
文章からすれば、芭蕉が表現したかった表現と、レミンスキーがしたかった表現は異なっていること、それは日本とポルトガルの文化によって生じることが書かれています。
そうであれば、この例えからざっくりと、言葉の持つイメージは風土や文化によって異なるものである、つまり言葉は絶対的な意味を持つものではなく、文化や風習によってその意味が変わる流動的かつ相対的なものであるというを筆者は言いたいんだなということがわかるわけです。
そうであれば冒頭の文というのはこのように考えることができます。
すなわち、言葉はそれを知った時点(ことばの獲得)で一義的に意味が確定するものではなく、生まれ育った風土や文化を知ることで、(日本の文化など)逆に元々知っていた言葉(例えば春)を再定義されるものであるということなのです。
だから、言葉は文化や風習により培われた"前言語的な未発の意識との間に保存される記憶や痛み"によって再定義されるものであり、言葉本来がもつ意味によって定義されるものではないということを言いたいのです。
このような文意に従って、問題を解くことになります。
まずAについては3つ目のAから考えるのがいいと思います。
言葉はもともとある自分自身の経験などで得られた住んでいる土地の文化や風習(つまり自分自身)などを投影するものであり、言葉によって自分自身を定義するものではありません。
このような意味になりうるのは本質的という単語になるのです。(質問者様が選んだ意識的は今回言葉を意識するか否かということが全く文章中で問題となっていないので不正解ということになります。)
また次の問題に関しても、上記の文章の意味からすると質問者様の選んだ解答が間違っていることがわかると思います。
すなわち、日本語を学んで、言語以前のものを学ぶというのは日本語によって自らが住む日本の文化や風習を知るという意味になります。そうではなく、前言語的な意識によって言葉が定義されるという内容を選ぶべきなので、5が正解となります。
問6は純粋に適当でないものを選ぶだけです。
興奮した理由が下線部後につらつらと書かれているのでそれに該当しないものを書くことになります。
1は一言も書いてないので答えになるのです。
また、文章の主題とも全く異なります。
1はブラジルの芭蕉の俳句は日本の風景と全く同じものを書いているといっていますが、言葉が同一だからといって、言葉の意味がそもそも文化や風習によって異なるため、同じ風景を書いていたとは限りません。
問7はおそらく4でしょう。
これも文章の意味から考えれば当たり前のことでそもそもこの文章のテーマが言葉は文化や風習によって異なることです。
そうすると日本人とブラジル人が同じ言葉に対するイメージが違うから想像する風景が違うとするのが文章の意味に合致します。
問8についても文章の意味がわかればほとんど消えます。
今回、筆者は言葉は不確実なものであると述べています。
そうであれば、確実な意味を持つことの象徴である、専門用語で、人類学者は様子を記録すべきだとしている1.4はまず消すべきです。
また文化や風習によって表現の意味が異なるという文章のテーマからすれば、日常と異なる文化を日常生活を充実させるために必要であるという記述はズレるのでこれも消えます。
残ったのは質問者様が選んだものと正解の二択ですが、より適切なのは明確に専門用語の使用を否定しており、自身と異なる文化を体験している人たちの言葉では表せない感覚を拾い上げるということが記載されている2であることがわかります。
問9は完全に質問者様が選んだことを言ってるので解説は割愛します。
最後の問題ですが、言葉の意味に焦点を絞っている4.5は言葉の意味は不確実という文章のテーマと全くズレるので真っ先に消すべきです。
そして、3は芭蕉が重要ではないなんて一言も言ってないので消えるべきです。
また、1についても日本の俳諧の精神が文化や風習の違う異国に伝来するというのは文化や風習が各国により異なることを前提とする文章の意味に反するので消えます。
残ったのは2で、ことばはその意味だけでなく、視覚的な情報により訴えるというのは、バッチリ書いてあるので、正解になります。
以上で解説は終了しますが、この問題から学べるのは一見して意味が不明の場合、具体例を見ることです。
そういう場合、具体例が詳しく書かれていることが多いため、具体例から、筆者の主張を類推し、筆者の説明部分と一致するかを当てはめていくことになります。