✨ Jawaban Terbaik ✨
乾燥帯かどうかの基準は「乾燥限界」という数値を計算しないといけません。
その計算には、年平均気温と月別の平均気温、降水量を使います。
⑤のデータから、一番降水量が多い1月は気温が高く、降水量が少ないときは気温が低いことがわかります。
この場合、「冬に乾燥している」と言えるかどうかを考えます。
たいていの場合、夏に降水量が多くなるので、「冬に乾燥している」と言える基準は、最も降水量が少ないときが最も多いときの10分の1未満であることが条件です。
このデータでは、4.0と49.3なので、10分の1未満で、「冬に乾燥している」ということになります。
このときの「乾燥限界」の式は、
(年平均気温(℃)+14)✕20=(21.6+14)✕20=712㎜ となり、
年降水量が712㎜未満だと「乾燥帯」のうちのステップ気候、そして、その半分の356㎜未満だと砂漠気候になります。
⑤の年降水量は267.1㎜なので、砂漠気候に分類されます。
…と言うやり方(教科書にも載っています)なのですが、何でこんな面倒なことをさせるんでしょうね。この問題…。
実際に、入試でこういう問題が出ることはないだろうと思います。
万が一出題される(私立大とかで)としても、計算式ややり方は、書いてあるでしょう。
ここで大切なことは、ケッペンの気候区分は、気温と降水量で決めるようになっていること、乾燥帯は気温と降水量のデータで乾燥限界を計算して決定する、ということを知っておくことでしょう。













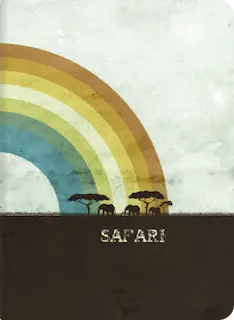


詳しく説明して下さってありがとうございます!助かりました🙇♀️