✨ Jawaban Terbaik ✨
カルボニル酸素を求電子的にして、カルボニル炭素が求核攻撃されやすいようにするってのが求核付加反応です。
YがClやOの場合、こいつらは電気陰性度が大きいので、Y上に正電荷があるとエネルギー的に不安定になります。Y=Nとかだったら正電荷があった方が寧ろ安定になります。
エネルギーと波長・振動数は、E=hν=hc/λの関係があるため、短波長ほど振動数は大きくなり、エネルギーも大きくなります。
そう考えると、反応性と振動数の関係って何となくわかってきません?
合ってます。
良かった……笑
凄くスッキリしました!
















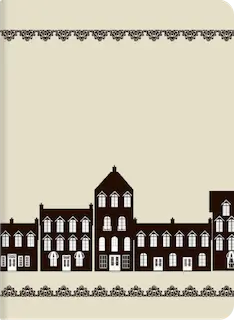
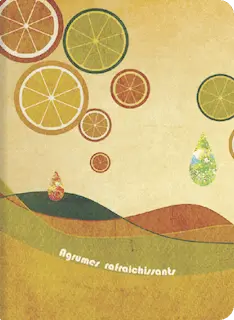

回答して下さりありがとうございます!
確認なのですが、「エネルギーが大きい」というのは「より不安定なもの」ということで合ってるでしょうか?
そうであれば、共鳴寄与体がエネルギー的に不安定であるものの方が振動数が大きくなる、ということですよね?
それなら解答とも合っていますし、納得がいきます!わかりやすい説明、ありがとうございます!