Answers
Answers
主にイオン結合であることが多いです。
ただ教科書でも「非金属元素と金属元素の結合がイオン結合である」と説明されがちなので誤解されやすいのですが、実はイオン結合の定義そのものが非金属元素と金属元素の結合というわけではないです。
共有結合とイオン結合ははっきりと境界線を引くのは難しく、共有結合っぽい金属結合もあります。しっかりと考えると、電子軌道の相互作用の話になって難しいのですが、簡単に説明してみましょう。
例えば炭素同士が繋がった共有結合では、炭素がそれぞれ一つずつ電子を提供し合いますね。それをしっかりと考えると軌道の話になります。元々は両方とも一つずつ電子の軌道があり、そこに一つずつ電子が入っています。それが相互作用することで1つの新しい軌道を作り、そこに先程の二つの電子が入ります。二つの電子は二つの炭素原子の軌道が「共有」しているので共有電子対と呼ばれますね!その新しい軌道というのはどんな形かというと、実は二つの炭素原子の軌道を適当な割合にして足し合わせたものです。それではどっちがどれくらいの割合含まれているかは元々の軌道のエネルギー準位(簡単に言えば炭素原子の電気陰性度です)によって異なります。今回は両方ともエネルギーが変わらないので、二つの軌道が等分配されることになります。
一方で金属と非金属の場合、金属が極端にエネルギーが高く(電気陰性度が小さく)、非金属が極端に低い(電気陰性度が大きい)ので、二つの軌道が作用しても、新しい軌道の形はほとんど非金属元素の方の軌道が反映されます。つまり、電気陰性度が大きな非金属元素の方に電子が局在している、ということができます。明確に±がわかれているので、このことを近似的に「クーロン力」による結合だとみなすことができます。これがイオン結合です。ただ、これは互いの電気陰性度の差が十分大きいから成り立つもので、同程度になってくると共有結合性も無視できなくなります。つまり電気陰性度の大きな金属元素や、小さな非金属元素になってくると共有結合っぽくなります。
また、ここでは出てきませんが、金属結合ではすべての原子がすべての電子(自由電子)を提供しあって軌道を作り、安定化しています。
グダグダ言いましたが、言いたいのは共有結合とイオン結合ははっきり分かれてなくて、PHの酸性とアルカリ性みたいにグラデーションになっているということです。そして、非金属ー金属の組み合わせはグラデーションのイオン結合寄りにあるものが多いということです。
共有結合である場合が多いと思います。
電子を引きつける力が強いもの同士だと、真ん中らへんに電子がガチッと引き付けられているイメージ。(共有結合)
片方が強く片方が弱いとその強い片方にほとんど電子が集中していて、結局プラスマイナスがくっついているかんじ。(イオン結合)
どちらも弱いと共有電子は比較的自由に動くことができるイメージ。(金属結合)
なんか軌道の話とか難しいこと言いましたが、上の3つをなんとなーく理解してくれればいいです笑!
え、めっちゃわかりやすいです笑⊂(◉‿◉)つ
ありがとうございます!!(*^^*)
Pengguna yang melihat pertanyaan ini
juga melihat pertanyaan-pertanyaan ini 😉











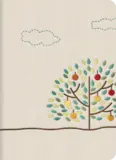



ありがとうございます!!