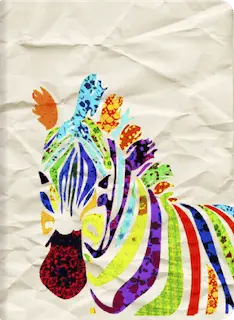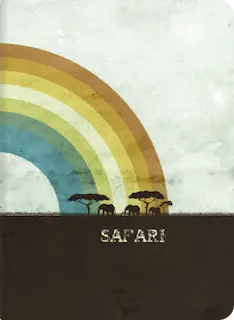Pharmacy
Mahasiswa
来週テストなのですが全く分かりません
回答がわかる方教えてください。お願いします
■ 1/3
令和6年度3年生前期 くすりの生体内運命 追加評価対策問題集
問1 炭火焼肉を連日摂取した場合、 CYP1A1/1A2 が誘導される可能性が高いが、 鉄板焼肉を連日摂取し
ても CYP1A1/1A2が誘導される可能性が低い理由について、 簡潔に説明しなさい。
問2 分子量が同じ薬物の糸球体ろ過において、 負電荷の薬物は正電荷の薬物よりろ過されにくい理由
を簡潔に説明しなさい。
問3 薬物動態学的相互作用が関与する重篤な薬害事件であるソリブジン薬害事件 (日本)とテルフェナ
ジン薬害事件 (米国)が発症したが、 それらの薬害について簡潔に説明しなさい。
問4 高血圧の治療薬のアンジオテンシン変換酵素阻害薬であるエナラプリルまたはテモカプリルを腎
機能障害患者に投与することになり、 どちらの薬剤を処方することが推奨されるかを医師から問われた
場合、 あなたは両薬物の薬物動態の違いからどちらを推奨しますか。 また、 そのような薬物動態的な違い
が生じる原因について、 明確に記載しなさい。
問5 免疫抑制薬シクロスポリンと抗菌薬リファンピシンを併用した場合に生じる薬物相互作用につい
て簡潔に説明しなさい。
問6 薬物の主排泄経路の特徴として、 尿中に排泄されやすい (腎排泄型) 薬物と胆汁中に排泄されやす
い(肝排泄型) 薬物が存在する。 これらの薬物の主排泄経路を決定する要因として、 ①薬物の分子量、 ②
薬物の脂溶性、 ③薬物のタンパク結合性、 ④抱合体への代謝、 ⑤ 肝臓と腎臓でのトランスポーターの発現
の違いがある。 胆汁中排泄されやすい薬物のそれぞれ ①~⑤の要因の特徴について説明しなさい。
問7 薬物の吸収に影響する因子を列挙し、 それぞれの因子について簡潔に説明しなさい。
問8 一つの薬物が薬物代謝酵素の阻害作用と誘導作用の相反する二相性の作用を示すことがある。 こ
のような二相性の作用を示すことが生じる原因について簡潔に説明しなさい。
問9 ワルファリンと血清アルブミンの結合がフェニルブタゾンによって競合的に阻害され、 ワルファ
リンの抗凝血作用が一過性に増強されるが、 その増強は一過性であり、 重篤な副作用にはなりにくい (一
過性の出血傾向)。 この様な現象が起こる理由について簡潔に説明しなさい。
問 10 代謝過程での薬物間相互作用が生じた場合、 可逆的阻害よりも不可逆的阻害の方が重篤な副作用
に繋がるケースが多い理由について簡潔に説明しなさい。
問11 薬物代謝酵素の阻害および誘導のメカニズムについて、例を挙げて簡潔に説明しなさい。
問 12 血漿タンパク結合率が高い薬物が投与された際に、 併用薬によって結合の競合的置換が生じる場
合がある。 その際に血漿タンパク結合率が高い薬物の血中からの消失速度が速くなる可能性が生じるこ
とがある。 その理由について簡潔に説明しなさい。
問 13 エタノールにより誘導されるアセトアミノフェンの肝毒性について、 代謝不活性化と代謝活性化
を含めて簡潔に説明しなさい。
問 14 ピロリ菌除去の第一選択薬として、 プロトンポンプ阻害剤(例えばオメプラゾール) と二種類の
抗生物質(アモキシシリンとクラリスロマイシン) の三種類である。 これらの第一選択薬の除菌効果と
CYP2C19 の遺伝子多型の関係について簡潔に説明しなさい。
問15 プロベネシドとベンズブロマロンはともに痛風治療薬であるが、 どちらか一方の薬物のみがドー
ピングの対象薬である。 同じ薬効にもかかわらず、 一方だけがドーピング対象薬である理由を簡潔に説明
しなさい。
問16 酸性薬物より塩基性薬物の方が母乳中へ移行しやすい理由について簡潔に説明しなさい。
問 17 投与薬物が薬物代謝酵素を阻害する場合と誘導する場合では、 併用薬あるいは自分自身の薬物に
対してどのような現象 (薬物相互作用) が生じるかを簡潔に説明しなさい。
問 18 高齢者は若年者と比べて、 ジアゼパムなどの脂溶性薬物の分布容積は増加し、アンチピリンなど
の水溶性薬物の分布容積が減少する要因について簡潔に説明しなさい。
問 19 アゾール系抗真菌薬のイトラコナゾールの血中濃度は H2受容体拮抗薬ファモチジンの併用によ
り血中濃度が低下するが、 その原因について説明しなさい。
問 20 薬物代謝酵素の阻害あるいは誘導による薬物相互作用において、 誘導が阻害より危険なケースが
あるが、その理由について、 解熱鎮痛薬アセトアミノフェンを典型例として簡潔に説明しなさい。
問 21 シクロスポリンの服用は、 HMG-CoA 還元酵素阻害薬ロスバスタチンの血中濃度を上昇させ、横紋
筋融解症の発症にいたる可能性があるが、 その要因について簡潔に説明しなさい。
問22 水溶性ビタミン類であるリボフラビン(ビタミンB2) および高脂溶性で難水溶性薬物であるイン
ドメタシンファルネシルは、いずれも空腹時より食後の方が、 消化管からの吸収性が上昇するが、 その原
因は両薬物で異なっている。 リボフラビンとインドメタシンファルネシルの吸収性が食後投与の方が上
昇するそれぞれの原因について説明しなさい。
問23 分布容積 (Vd) が、 ① 血漿容積 (3L)から細胞外液容積 (12L) に等しい薬物、 ② 細胞外容積
から総体液量(36L) に等しい薬物、 ③ 総体液量に等しい薬物および④ 総体液量以上の容積の薬物の
それぞれの特徴について簡潔に説明しなさい。
問24 アゾール系抗真菌薬によるシトクロムP450 の阻害作用のメカニズムについて説明しなさい。
問25 初回通過効果と生物学的利用率の関係について簡潔に説明しなさい。
問26 薬物動態学的相互作用と薬力学的相互作用について簡潔に説明しなさい。
問27 薬物の分布容積について説明しなさい。
問 28 リドカイン・プロプラノロール・イミプラミンなどの塩基性薬物が結合する血漿タンパク質は何
か。 また、このタンパク質が急性期タンパク質とも呼ばれているが、 その理由について説明しなさい。
問 29 薬物の血漿タンパク結合と分布容積の関係を定量的に説明しなさい。
問30 プロドラッグと活性代謝物について、 例を挙げて説明しなさい。
Answers
No answer yet
Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?
Pengguna yang melihat pertanyaan ini
juga melihat pertanyaan-pertanyaan ini 😉