✨ Jawaban Terbaik ✨
会話の「カ」の内容は後背湿地の特徴を言っていますね。
地形図を見ると、鬼怒川の両岸に土手のきごうがあって、堤防が築かれているようです。
小学校前駅から橋までが後背湿地で、「田」の記号が並んでいます。
橋を渡って、飛山城跡駅に着くあたりで、崖が見えて、城跡があるのが河岸段丘かもしれません。
さて、「川に沿った土崖の方向を見ると、自然堤防のように盛り上がっているのではなく、むしろ凹んでいるんですが」ということですが、その「土崖」が「土手」なのか「崖=段丘崖」を指しているのか、どっちなのでしょうか?
「カ」の文章は、小学校前駅から橋までの説明なので、この範囲には「河岸段丘のような地形」はありません。
だから、あなたの指摘はあてはまりません。
この地図の、小学校前駅と橋の間には、後背湿地が広がっていますが、自然堤防らしきものはありません。
また、段丘崖もありませんが、どこにあると思いますか。
地図の画像に印をつけてみてください。
後背湿地というよりも、氾濫原ですね。このあたりは。
低湿地であることは共通していますが、後背湿地だと考えると、自然堤防はどこ?って探してしまいますが、ここにはなさそうです。
繰り返しますが、段丘崖は、川の西側にはないようです。
回答者様が土手と矢印をつけられた土崖の地図記号のことです。つまり私が言いたいのは、川が氾濫しても下の地図の赤い線沿いの土崖による凹みの部分に水が溜まって、水田のあるところまでは水が氾濫しないのではないか、ということです
土手は、最近人工的に作られたもので、水田がある湿地帯は、それ以前にできたものです。
なるほど、ありがとうございました
よかった、わかってもらえて。
下の図に、赤いマーカーの線で描いた土手は、川が氾濫して水田が被害を受けるのを防ぐために作られたものです。
水田のある一帯は、この土手がなかった頃に、洪水が頻繁に発生して、湿地になっていたものと考えられます。

















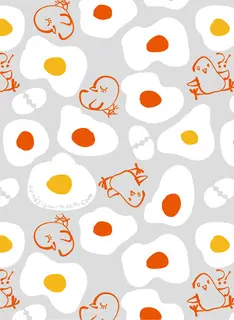

後背湿地がある場合、1枚目の写真のように河道付近は盛り上がっているはずですが、土手の部分の土崖の地図記号の方向を見ると、二枚目の写真の下のように、凹んでしまっているので、1枚目のように、水が溢れ出して、後背湿地ができるといことはないのでは無いかということです