ノートテキスト
ページ1:
●<エネルギーの種類とパラメータ> 物理量(エネルギーやパラメ タ)の注意点 ○物理化学では、たくさんの物理量を扱う →数値×単位 ○用語は日本語または英語で表すが、計算の時は記号を扱う V 用語と記号をセットで覚える <エネルギーの種類> ○ポテンシャルエネルギー(記号: EP) potential ○運動エネル ギー(記号:Ek) kinetic (記号:H) ○内部エネルギー(記号: U) ○エンタルピ - ・ギブスエネルギー(記号:G ) ○ヘルムホルツエネルギー(記号:A) <エネルギーを表すパラメータ> ケルビン 温度(記号T,単位K) m → Temperature 立方メートル 体積(記号V,単位m3) "volume" 記号は英語由来のことが多いので、 ・合わせて覚えると良い パスカル 圧力(記号P,単位Pa) Pressure ジュールパーケルビン エントロピー (記号S,単位 JK-) ⇒ 物理化学 <温度> 日常で使う温度=セルシウス温度 J 1気圧における水の融点を0℃、沸点を 定義) 100℃とした温度 L ケルビン 科学で使う温度=絶対温度(記号で、単位K) 「すべての物質が運動しなくなる温度を 定義) 絶対零度とする温度 J 絶対零度(OK)をセルシウス温度で表す→-273.15'c
ページ2:
<セルシウス温度と絶対温度の関係> 絶対温度 セルシウス温度 ok -273.15'c <絶対温度の特徴> 73.15k 173.15K 263.15k 273.15K 283.15k -200c -100'c -1010 O'C 10'℃ W 1'c=1k Vy T(K)=t()+273.15℃ 絶対温度 セルシウス温度 セルシウス温度: 0℃より低い 温度では負の値 絶対温度 = 正の温度 〈体積〉 1m メートル IUPAC →> 長さの単位 m 体積 →V=1mx 1 m x1m 1m² 立方メートル 体積の単位→ m3 1m CCC C C C C C C 〈力と圧力〉 ニュートン 力(記号F,単位N) ○力は質量m(kg)と加速度a(ms2)で表されるが、地球上の重力場 では、加速度(ms)を用いて。 F=mg... ① 0m = 1.0kg,g=9.81ms-2を式①に代入する F=1.0kg×9.81ms -2 = ON=kgms-z 圧力(記号、単位Pa) 9.8kgms2=9.8N m ○定義:単位面積にかかる力 カ(F) ☆ 面積(A) } P = = = = 0 F A OF=1.0N,A=1.0m²を式②に代入する P = 1.0N 1.0m² Pa=Nm-2 =1.0Nm²=1.0Pa www
ページ3:
〈静水圧> ○気圧=空気の塊が力を加えている 0 0 この円柱(体積V=Axh)の質量は 密度(kgm3)の物体が底面積A(m²)で 高さ(m)の円柱に入 ている m=0xAxh…③ となる 物体が底面に与える力は 高さん 密度 (kgm²) (m) F =mg = xxAxh g ④ となる 0 式④を圧力の式②に代入すると 底面積A(m²) P = E E, PxAxhx 9 A ・phg⑤ A ○式⑤を静水圧という。 〈圧力の表し方> ○圧力の単位 水銀柱の高さ(mmHg トル = torr) アトム 0 海面の気圧=約1気圧にlatm) Elatm =760 mm Hg = 760mmHg = 760 torr 1.013×108Pa3 <標準状態> 圧力:1気圧 Ok , O'C(温度) NO 103Pa →現実的ではない 105 Pa 温度:環境温度に近い25℃ 標準状態はP=105Pa,25′の状態を示す
Recommended
Recommended
Undergraduate
物理
熱力学の定圧モル熱容量とエントロピーの問題です。 回答は1なのですが、計算方法が分かりません。 途中式をご教授していただきたいです。よろしくお願いします。
Undergraduate
物理
107番についてです (2)まで正解です (3)以降で自分が書いてることのうち何を間違えているのか指摘してほしいです 習っている先生が合成容量を使わない方針なので、その方針で指摘していただけると助かります
Undergraduate
物理
大学の物理力学です 解法が分かりません。 解答と解説(公式も含めて)を教えていただきたいです
Undergraduate
物理
「計算の基礎から学ぶ土木構造力学」という参考書の応力図の問題です。この問題4・3の⑷を解説していただきたいです。解説にある1.3mと2.7mの出し方がわからないのですが、3枚目写真にあるまとめページの右中央にあるXをだす式を使って計算してもでできません。その箇所だけで構いませんので、計算方法を教えていただきたいです。
Undergraduate
物理
不確定性原理の「思考実験」は本質的理解を妨げる?その意義と限界を教えてください。 こんにちは。ハイゼンベルクの不確定性原理について学んでいます。 最近、不確定性原理の核心は「観測による干渉や誤差」ではなく、**「量子的な粒子は、観測があろうとなかろうと、そもそも位置と運動量のようなペアとなる物理量を同時に確定した値として持っていない」**という、量子の本質的な性質にあると理解しました。 この理解を踏まえた上で、一つ疑問が生じています。 それは、不確定性原理を説明する際によく用いられる**「思考実験」の役割**についてです。 例えば、「電子の位置を見ようと光子を当てると、その衝突で電子の運動量が変わってしまう」といった説明です。 この思考実験は、「観測という行為が対象に影響を与える」という一面を分かりやすく示しているとは思います。 しかし、不確定性の本質が「観測とは無関係に元々決まっていない」のだとすれば、この種の思考実験は、かえって「不確定性の原因は観測にある」という誤解を招きやすく、量子の本質的な性質から目を逸らさせてしまうのではないかと感じるのです。 そこで、物理に詳しい方にお伺いしたいのですが、 このような「観測による擾乱」を強調する思考実験は、不確定性原理の「観測とは無関係な本質」を理解する上で、実際にはどのような意義や位置づけを持つのでしょうか? もしこの思考実験が誤解を招く可能性があるのであれば、なぜ今でも不確定性原理の導入として広く使われ続けているのでしょうか? 歴史的な経緯や、教育上の何らかのメリットがあるのでしょうか? 「観測とは無関係に、元々位置と運動量は同時に確定していない」という量子の本質的な性質を、より直感的に(あるいは思考実験とは異なる形で)理解しやすくするための、何か良い例えや説明方法があれば教えていただけますでしょうか? 「観測のせいではない」という本質を掴んだつもりでも、この思考実験の存在が頭の中で引っかかっています。 この点について、皆様のご意見や知識をお聞かせいただけると大変幸いです。 よろしくお願いいたします。
Undergraduate
物理
放射線物理学の問題です。 教科書を見ても解き方が載っていなくてどの公式を使ったらいいのかが分からないので解説していただきたいです。
Undergraduate
物理
物理の問題です Aに対するBの相対速度 A) v=5.0m/s B)v=3.0m/s 西向き(左)を正とする VAB=(+3.0)−(+5.0) =−2.0m/s この場合答え方って東向き-2.0m/s になるのでしょうか?
Undergraduate
物理
10気圧をPaにした時いくつになる?
Undergraduate
物理
この問題を解き方の過程も加えて解いていただきたいです。
Undergraduate
物理








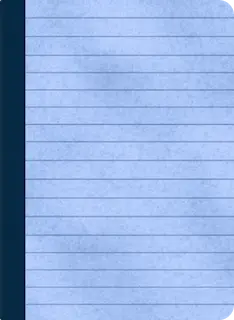


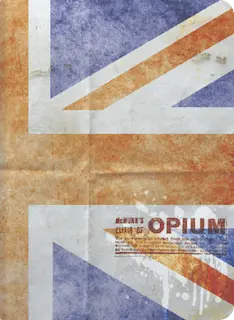


Comment
No comments yet