ノートテキスト
ページ1:
No. 植生の成り立ち・遷移 さまざまな植生 Date ☆(バイオーム(生物群条)):ある地域に生息する植物や動物などすべての生物の集団。 生物は互いに関係をもちながらそれぞれ特徴のあるバイオームを形成しているが、 陸上のバイオームは(植生)に依存して成り立つ。 ☆(植生):そこに生育する植物の集まり。 生物の生活に影響を及ぼしている外界を、その生物にとっての(環境)という。 環境には、温度・光・大気・水・土壌などの(非生物的環境)と、 その生物に影響を与える(生物的環境)がある。 植物の生活形 ☆(生活形):植物は、それぞれ生育する環境に適応した生活様式と形態をしている。 ○葉の形態による分類0 [広葉樹〕:幅広く扁平な葉をもつ。 NO.1. 〔針葉樹〕:細く鋭い葉をもつ。 ○落葉するかどうかによる分類〇 〔落葉樹]:冬季や乾季など生育不良な時期にすべての葉を落とす。 〔常緑樹〕:すべての葉を落とす時期がない。 ○冬芽(休眠芽)の位置による分類〇 高緯度地域や標高の高い場所のような寒冷な地域では、 (地表植物)や(半地中植物)の割合が高くなることが知られている。 砂漠などには、著しい乾燥の時期を種子で乗り越える(一年生植物)が多い。 地上部は枯れても地下部が存在して次の成長時期に備える(多年生植物)や、 冬芽を水面下につける(水生植物)もある。 名称 分類名 スギ、ツツジ コケモモ、オク 地上植物 タンポポ、ススキ ジャガイモ,27 地表植物 半地中植物 地中植物 冬芽の地表からの位置 30cm以上 30cm以下 地表 (0cm) 地中 KOKUYO LOOSE EAI -83 AT 7 da
ページ2:
植生の成り立ちと遷移 1植物の生活形+α ☆(冬芽(休眠芽)):生育に適さない冬季や乾季などに植物がつける。 低温や乾燥に耐えることができる芽 ☆(ラウンケルの生活形):冬芽の位置によって植物を分類したもの。 森林の階層構造 よく発達した森林には、高さに応じた(階層構造)がみられ、 高木、亜高木、低木、草層、地表層からなる。 森林の最上部の(林冠)から地面に近い部分の(林床)にかけて、 到達する(光量)が減少するため、それぞれの層では、その光量に 適応した植物が生育している。 0.1 10 相対照度(%) 100' (林冠) 30 高木 ・・・森林の最上部のこと、 20 亜高木 10 低木 地表層 0 葉などに太陽光が遮られるため、 (林床) ・地面に近い部分のこと 草本層 地表面からの音さく 森林の下層ほど到達する光量が減少する。 |土壌の構造+α ☆(リター):森林における落葉や落枝のこと。 海洋や草原のバイオームに比べ、森林のバイオームでは リター量が多く、リターを直接食物とする生物が多く生息する。 さらにこれを間接的に捕食する生物もいて、 リターから始まる食物連鎖が成立している。
ページ3:
植生の成り立ちと遷移
No.
Date.
土壌の構造
土壌は、岩石が水、温度、空気などの影響を受けて(風化)したものと、
植物の枯死体などの有機物が土壌中の微生物によって
(分解)されたものからできる。
森林の土壌は、垂直方向に(層状構造)がみられる。
☆落葉層
("I
(落葉)や(落枝)などの
(有機物)でできた層。
☆腐植層
・落葉や落枝が微生物による分解を
受けた有機物でできた層。
☆岩石が風化した層
[!!
(母材(母岩))と呼ばれる岩石が
風化した、有機物に乏しい層。
☆風化前の岩石母材(母)
風化前の岩石の層。
|光合成速度|
植物が単位時間あたりに行う呼吸量や光合成量は、
それぞれ(呼吸速度)、(光合成速度)として測定される。
植物は光がない状態では呼吸しか行えないが、
光が照射されている状態では呼吸と同時に光合成を行う。
詳しくは
し
next page
KOKUYO 100SE-LEAF -63607 med 33 inv
ページ4:
Date 光合成速度 ☆(呼吸速度) ・光がない状態で、植物が 呼吸でCO2を放出する速度。 光照射の有無にかかわらず、 常に一定の速度で呼吸が 吸 ・牧+ CO2 行われているものとする。 *実際に、呼吸速度は光の速さが 強くなるにつれて小さくなる。 吸収速度 -420 光飽和点 (光補償点) 見かけの 光合成 速度 光の 強さ 呼吸 速度 光合成速度 ☆見かけの光合成速度 植物の見かけ上のCO2吸収速度。 光照射下で、植物が光合成に 必要なCO2を吸収する速度。 暗) (明) ☆光合成速度 光合成速度=見かけの光合成速度+呼吸速度 が、 実際に植物が行っている光合成速度。 これ以上光を強くしても光合成速度が大きくならない光の強さ。 ☆光飽和点 ☆光補償点 光合成速度=呼吸速度 見かけ上のCO2の出入りが0(光かけの光合成速度が0)になるときの 光の強さ。
ページ5:
Date 【光の強さと光合成速度1 放出 ① 2 ③(光補償点)(光飽和点) 見かけの 光合成 速度 速度 (光合成速度) 光の強さ (明) ①光の強さ〇のとき、 暗黒下では光合成は行われず、 呼吸しか行われていない。 0- 見かけの光合成速度が負(マイナス)と なっている。 呼吸 速度 光合成 速度 ②光補償点以下のとき 2 0 呼吸 光合成 速度 速度 光補償点以下では光合成速度が 呼吸速度を下回っている。 見かけの光合成速度が負(マイナス)と なっている。
ページ6:
[光の強さと光合成速度1 ③光補償点 ↑ 0 呼吸 光合成 速度 光補償点では呼吸速度と 光合成速度がしい。 見かけの光合成速度が0となっている。 速度 ④ 光補償点以上のとき、 光補償点以上では光合成速度が 呼吸速度を上回っている。 0 見かけの光合成速度が正(プラス)と なっている。 呼吸 光合成 速度 速度 1陽生植物と陰性植物 ☆(陽生植物) →強い光の下で生育する植物 (光飽和点)が高いため、(最大光合成速度)が大きい。 そのため、強光下での見かけの光合成速度が大きく、 多くの有機物を合成することが可能なので、 強光化での生育に有利である。 ☆(陰生植物) →森林内など、比較的弱い光しか当たらない条件で生育できる植物。 (呼吸速度)が小さく、(光補償点)が低い。 そのため、弱い光の下でも見かけの光合成速度が正になりやすく、 弱光下でも生育が可能である。
ページ7:
光環境と植物 1個体の植物においても、日当たりのよい場所につく(腸薬)は (陽生植物)と同様の特徴を、日当たりの悪い場所につく(陰葉)は (陰生植物)と同様の特徴を示す。 (陽葉)は(陰葉)よりも厚みがあって、小さいという傾向がある。 (植生の遷移 ☆(遷移)…ある地域の植生が、時間の経過とともに 一定の方向性をもって移り変わっていくこと。 (一次遷移)・・・裸地から始まる。 (二次遷移)…山火事の跡地などから始まる。 遷移の種類(土壌と植生の有無) 初期の状態 始まる場所の 特徴 土壌の形成や植物の なし 具体例 火山噴火による 溶岩台地、新しく侵入に時間がかかるため、 一次遷移 (株地からスタート) 隆起した島など。 極相に到達するまでに 時間がかかる。 土壌がすでに形成されて 生育に必要な水や養分が 放棄された耕作地おり、種子や地下茎の 山火事の跡地 伐採された森林の供給される。そのため、 あり 二次遷移 土壌中に 植物種子など あり 跡地など 一次遷移に比べて 極相に到達するまでの 時間が短い。
ページ8:
一次遷移 ①裸地:荒原 (裸地への植物などの侵入 まず、乾燥や貧栄養に耐えることができる(コケ植物)や(地衣類)などが 裸地に侵入する。 遷移の初期段階にあらわれる植物は、(先駆植物(パイオニア植物))と 呼ばれる。 ◎(乾性遷移)…陸上の裸地から始まる遷移 ◎(湿性遷移)・湖沼などから始まる遷移 ②草原 ススキ、チガヤなど 〈草原への遷移〉 コケ植物や地衣類などの枯死体の蓄積や岩石の風化によって(土壌)が 形成されると、乾燥や貧栄養に強く成長の速い(草本植物)が侵入する。 根が岩石の風化を促進させる作用も加わり、さらに土壌が発達する。 ③低木林 オオバヤシャブシ、ヤマツツジなど <③~④陽樹林の成立〉 強い光が得られる草原には、(陽樹)の(木本植物)が侵入する。 強光下で成長が速く、背丈の低い陽樹(オオバヤシャブシなど)が散在する本が 形成されていく。
ページ9:
植生の成り立ちと遷移 一次遷移 ] ④陽樹林 ⑤混交林 アカマツ、クロマツなど アカマツ、シイ、カシなど No. Date (④~⑤陽樹林~陰樹林など〉 (陽樹)が育ち、(陽樹林)の林床付近の光が減少すると、 光補償点の高い陽樹の芽生えは生育したくなる。 (陰樹)(シイノカシなど)の芽生えは光補償点が低いため生育できる。 そのため、陽樹と陰樹の(混交林)を経て、(陰樹林)へと移り変わる。 ⑥陰樹林=極相 (陰樹林の維持) 陰樹林の林床付近もかなり暗いが、陰樹の芽生えや幼木の 光補償点は低く、林床でも生育できるため、森林の構成樹は ほとんど変化しなくなる。(=極相) ○[一次遷移 火山噴火による溶岩流や大規模な地層の崩壊などによってできた 裸地から始まる(一次遷移)では、(裸地・荒原→草原→低木林→ 陽樹林→混交林→陰樹林)と変化する。 陰樹林の内部では(陽樹)の芽生えは育たないので、それ以上遷移が進まない。 この状態を(極相(クライマックス))という。
ページ10:
Daty 1先駆植物と極相樹種1 ☆(先駆植物)・遷移の初期段階にみられる植物種 1. 種子が小さく、散布能力大 ・乾燥・貧栄養に強い ・成長速度が速い ・小形で寿命が短い ・耐陰性が低い ☆(極相樹種)…極相段階でみられる樹種 ex) ススキノチガヤなど ex) シイ、カシノブナなど 1 種子が大きく、散布能力小 1 腐植に富む土壌が必要。 成長速度が遅い 大形で寿命が長い. ・耐陰性が高い 1ギャップの形成と極相の維持」 極相林においては、高木の枯死や台風などによる倒木によって。 (ギャップ)が形成されることがある。 ギャップでは部分的な(二次遷移)が進行することになり、このような森林 構成する樹木の入れ替わりを(ギャップ更新)という。 【湿性遷移 | 陸地から始まる(乾性遷移)に対して、(湖沼)などから始まり、(湿原)を経て 陸上の植生へと変化する(一次遷移)は(湿性遷移)と呼ばれる。 湿性遷移の後半の段階は、陸地から始まる乾性遷移と同じ過程をたどる。
ページ11:
植生の成り立ちと遷移 湿性遷移 ①長い年月の間に土砂が堆積して、水深が浅くなると、 No. Date クロモなどの(沈水植物)(植物体全体が水中に沈んでいる植物)が 繁茂する。 ②スイレンなどの(浮葉植物)(…水面に葉が浮かんでいる植物)が 水面を覆うようになると、沈水植物はしだいに姿を消す。 ③さらに土砂の流入によって水深が浅くなると、 ヨシなどの(抽水植物)(茎や葉の一部が水面上に出ている植物) 生育するようになる。 ④植物の枯死体や土砂が堆積して陸地が形成されるとし スゲ類などの(草原)となる。 ⑤さらに土壌の乾燥化が進むと、ハンノキなどの(樹木)が侵入する。 その後は、乾性遷移と同様の過程を経て、極相に到達する。 [まとめ] ・植物のCO2吸収速度は(光補償点)で(O)になり、 光飽和点以上の光の強さで(最大)となる。 ・(陽生植物)と(陰性植物)の光合成曲線は、 光補償点や光飽和点にちがいがある。 植生の遷移には、裸地から始まる(一次遷移)と、 山火の跡地などから始まる(二次遷移)がある。 湖沼 森林 KOKUYO LOOSE-LEAF -830AT maled 31
ページ12:
Thank you for reading
Other Search Results
Recommended
Recommended
Senior High
生物
有機物、ATP、グルコースの違いを教えてください😖
Senior High
生物
高校生物、植物の問題です 画像問2の選択肢A〜Eがなぜ○でなぜ×なのか理解できません。 画像2枚目が答えです。 よろしくお願いします。
Senior High
生物
この計算式がよく分からないので教えてほしいです! 比の式は分かるんですけど、数?がなんで15こと2こなのかが分からないです!💦
Senior High
生物
ウの選択肢のグラフですが、呼吸量が多い夜にphが高くなるのではないのですか?bだと思いました
Senior High
生物
至急です‼️ 明日期末テスト2日目で生物があるんですが 遺伝子の組み換え?がさっぱりわかりません!! 特に下の〇:〇:〇:〇みたいなところが分からないので教えていただけると幸いです!!
Senior High
生物
⑴の考え方がわからないです。数字が近いものを選ぶなら、3.2.1の順番ではないんですか?何故0の①がイに当てはまるのでしょうか?
Senior High
生物
セントラルドグマ=遺伝子の発現ですか
Senior High
生物
至急お願いします!!! 分かりやすく説明してください、図など、 今日テストなのにやばめです
Senior High
生物
(2)がわかりません。 b,cとdの違いが理解できず困っています。 なぜdは割り切れているのに3つ目の塩基になるのでしょうか⁇ よろしくお願いします🙇🏻♀️
Senior High
生物






















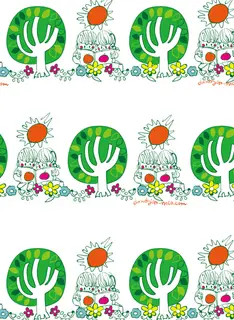

Comment
No comments yet